離婚時に生命保険は財産分与の対象に?受取人変更を忘れたらどうなる?

離婚をする際、生命保険も財産分与の対象となる場合があることをご存じでしょうか。
離婚時には、離婚届の提出や各種名義変更など様々な手続きが必要となります。そのため、生命保険に関する手続きを後回しにして、忘れてしまうことがあります。
しかし、生命保険も財産分与の対象となる場合があるため、離婚時にどうするかを話し合っておかないとトラブルになることがあります。
また、死亡保険金の受取人を変更せずに放置すると、万一の際に遺された家族が困ってしまうことも考えられるでしょう。
このような事態に陥らないよう、今回は離婚時の生命保険の取扱いについて解説していきます。
【ここをクリック】離婚時の生命保険の手続きについて知りたい方はソナミラでFP相談してみよう
生命保険は財産分与の対象となるか?
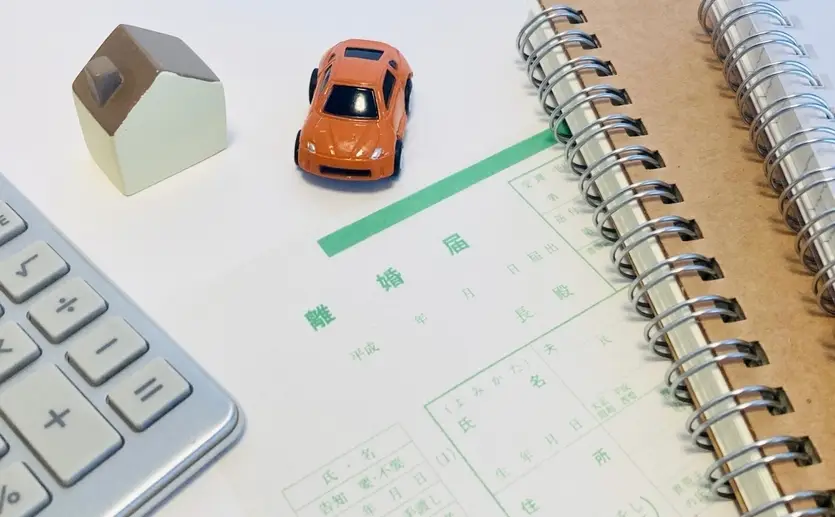
離婚をする際の財産分与において、生命保険は見落とされがちです。しかし、生命保険の種類によっては財産分与の対象となるものがあります。
財産分与の対象になる生命保険
解約時に、解約返戻金を受け取ることができる生命保険は、原則として夫婦の共有財産となるため、財産分与の対象になります。そして、その解約返戻金の額が財産分与の対象額となります。
解約返戻金が受取れる生命保険とは、多くの場合、貯蓄型の生命保険です。掛け捨て型の死亡保険や、掛け捨て型の医療保険には解約返戻金が原則無いため、財産分与の対象にはなりません。
加入している生命保険を確認する
離婚時の財産分与は、夫婦のその後の生活に関わる事なので、多くの方が気にするところではないでしょうか。
まずは、夫婦それぞれで加入している生命保険について、保険証券等を確認して、解約返戻金の有無を確認してみましょう。
そして解約返戻金のある生命保険契約が見つかった場合、その生命保険契約を財産分与の対象に含め、生命保険の見直し方法を話し合っておきましょう。
財産分与を想定した生命保険の見直し方法

財産分与の対象となる生命保険に加入している場合、現金化するために保険を解約したほうが良いのでしょうか。
必ずしも、その必要はありません。むしろ、解約は慎重に行った方が良いでしょう。
なぜなら、財産分与は離婚する際に夫婦で合意ができれば良く、全てを現金化して分ける必要はないからです。生命保険を解約せずに解決することができるかもしれません。
生命保険を新たに契約する場合、前回の契約時よりも被保険者年齢が上がっていたり、被保険者の健康状態が悪くなっていたりすることがあります。
一般的に被保険者年齢が上がると、保険料が高くなってしまいます。それに被保険者の健康状態によっては、そもそも生命保険に加入ができない事態も考えられます。
そこで慌てて解約するのではなく、次のような観点から今後の取扱いについて検討してみましょう。
財産分与という煩わしい問題を避けるために、離婚ではなく卒婚という選択肢もあります。気になる方は次の記事もチェックしてください。
▶【関連記事】卒婚した後の生活費は?離婚との違いやメリットとデメリットを解説
保険金の受取人を変更する
死亡保障のある保険契約は、多くの場合、契約者・被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻としていることでしょう。
併せて、契約者・被保険者を妻、死亡保険金受取人を夫として、それぞれで加入している場合が多いのではないでしょうか。
この様な契約形態の場合、死亡保険金受取人の変更を忘れずに行いましょう。
死亡保険金受取人の変更を行わずにいると、万一亡くなってしまった場合に、死亡保険金が元の配偶者に支払われてしまいます。
再婚している場合には、再婚後の配偶者に死亡保険金が支払われず、遺された家族の生活に支障をきたす恐れもあります。
死亡保険金の受取人変更は、契約している生命保険会社に必要な書類を提出することで行います。
すぐ再婚するのであれば、新しい配偶者を死亡保険金受取人に変更することができます。すぐ再婚しない場合でも、子どもがいる場合には、まずは子どもを死亡保険金受取人に変更すると良いでしょう。
このとき、両親を死亡保険金受取人に変更することもできますが、年齢的には自分よりも先に亡くなる可能性が高くなります。もし、先に死亡保険金受取人が亡くなった場合は、再度死亡保険金受取人の変更手続きが必要となります。
契約者を変更する
生命保険の契約は、「契約者=保険料を支払う人」、「被保険者=保険の対象となる人」となっています。そのため、契約者と被保険者が必ずしも同一人物である必要がなく、「契約者≠被保険者」となっている場合があります。
例えば、
- 契約者=夫
- 被保険者=妻
- 死亡保険金受取人=夫
という契約形態です。
- 契約者=妻
- 被保険者=夫
- 死亡保険金受取人=妻
という場合もあります。
保険の対象者である被保険者を変更することはできないため、この場合は、契約者と死亡保険金受取人の変更を検討することになります。
尚、保険によっては、契約者の変更が認められないこともありますので、具体的な手続きの前に保険会社に確認してください。
上記の契約形態の場合、保険を解約しないのであれば、被保険者が保険契約を引き取ることが一般的でしょう。
その場合、子どもがいる際は、
- 契約者=妻(夫)
- 被保険者=妻(夫)
- 死亡保険金受取人=子ども
とすることが多いです。
子どもがいない場合は、
- 契約者=妻(夫)
- 被保険者=妻(夫)
- 死亡保険金受取人=両親
とするケースが考えられます。
解約する前に次の保険を検討する
夫と妻の2人が関わる契約形態の場合、夫婦関係をリセットしたいという気持ちから、保険の解約を検討する人が多いと思われます。
しかしながら、先に述べた通り生命保険の契約は、契約時の被保険者の年齢や健康状況で保険料が上がることがあり、そもそも新たな保険に加入できないということも考えられます。
したがって、次のプロセスに沿って慎重に手続きをしましょう。
- その生命保険が今後も必要かどうかを検討する
- 保険が必要であれば、同じ保障内容で新たな保険に加入する場合の保険料や、現時点の健康状態で加入できるのかを確認する。
- 先に新しい保険の申し込みを行い、責任が開始されてから、元の保険を解約する。
新たな生命保険に申し込みをした段階では、被保険者の健康状態によって、保険会社から保険契約を断られてしまうことも考えられます。
しっかりと責任が開始されたことを確認してから、元の生命保険を解約するようにしましょう。また、がん保険には一般的に90日間の免責期間があります。この免責期間中は保障が受けられない点も理解しておきましょう。
【ここをクリック】財産分与などわからないことがある場合はソナミラでFP相談してみよう
離婚後に起こりやすい保険金請求トラブル

離婚後に生命保険の見直しを行わなかったことで、保険金の請求をめぐってトラブルになるケースがあります。このようなトラブルを発生させる原因を作らないために、次の点に注意していきましょう。
受取人が元配偶者のままだとどうなる?
生命保険契約の死亡保険金の受取人が元配偶者のままになっている場合、万が一の際には元配偶者が保険金を取得することになります。これは、現在の家族や子ども、再婚相手がいても、契約内容が優先されるためです。
生命保険金は受取人の固有財産です。契約内容において、死亡保険金受取人の指定が変更されない限り、遺言や法定相続とは別のルールが適用される点に注意しましょう。
「知らなかった」では済まされない!
生命保険金を受け取るためには、亡くなったことがわかる書類(死亡届)や、保険の契約に関する情報(保険証券の番号など)が必要になります。
もしこれらの情報を元の配偶者が知っていた場合、本来受け取るはずの人ではなく、元配偶者が保険金を先に請求してしまう可能性もあり得ます。こうなると、あとで「誰に支払うのが正しいのか」というトラブルになることもあるのです。
また、離婚したあとに名字が変わったり、引っ越したりしても、そのことを保険会社に伝えていなければ、契約は古い情報のままになってしまいます。そうすると、保険金の手続きがスムーズにできなかったり、書類が届かなかったりといった問題が起こることがあります。
保険の知識不足が招く「損失」
保険のことをよくわからないままそのままにしていると、いざというときに保険金をスムーズに受け取れず、せっかく入っていた保障が使えなくなってしまうこともあります。
また、離婚したあとも「保険はそのままでいい」と思っている人も多いですが、家族のかたちが変われば保険の内容も見直す必要が出てきます。
離婚後は生命保険を全体的に見直そう

離婚することで、家族構成やライフプランが変わります。
生命保険を解約するのか、契約を継続したまま契約者や死亡保険金受取人の変更を行うのか、離婚後の生活を見据えて、最良の選択をしましょう。
離婚時に保険を見直す、2つのポイントをご紹介します。
必要な保障額を再計算する
生命保険は、被保険者に万一のことがあった場合に、遺された家族が生活に困ることがないように加入するものです。そのため、離婚することで必要となる保障額が変わります。
新しいライフスタイルに合わせた保障額を再度計算する必要があるでしょう。
学資保険は継続を検討する
学資保険は、子どもが将来、高校や大学へ進学する際に備えて加入している保険です。
死亡や病気になった際の保障の目的もありますが、子どもの進学資金を貯めるために加入していることがほとんどでしょう。
そのため、学資保険は離婚しても解約せずに、契約を継続することをお勧めします。
離婚後に契約を継続する場合、契約者でない方が離婚時点での解約返戻金額の半分を現金で支払う形で財産分与を行うこともあります。
ただし、保険契約を引き継いだ契約者が、離婚後に保険料の支払いを続けることが難しくなる可能性もあります。もし保険料が生活を圧迫し、家計の負担になる場合は、保障の減額や払済保険への変更といった選択肢も検討しましょう。
離婚する時の生命保険見直しQ&A

離婚を考えたとき、「生命保険はどうすればいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。契約者や受取人の名義変更だけでなく、慰謝料や養育費の支払い、親権問題、財産分与、DVやモラハラといった事情も絡み合うため、非常に複雑です。
以下では、よくある疑問をQ&A形式で説明していきます。ここまで紹介してきた内容と合わせてみていきましょう。
Q1. 生命保険はどこまで財産分与の対象になるか?
基本的には、解約返戻金のある生命保険(いわゆる貯蓄型保険)が財産分与の対象となります。解約返戻金が発生しない掛け捨て型の保険は原則として対象外ですが、離婚調停や協議離婚の場で「実質的な価値がある」と判断されれば一部考慮されることもあります。具体的には、各保険の保険証券や契約内容を確認し、当該契約に解約返戻金があるかどうかを調査しましょう。
Q2. 死亡保険金の受取人を元配偶者から変更しないとどうなる?
先述したとおり、受取人が元配偶者のままだと、万一の場合にそのまま保険金が支払われてしまう可能性があります。保険金は民法上、受取人固有の財産とみなされるため、他の相続人がいても無効にはできません。「いずれ再婚する予定がある」「子どもを受取人にしたい」など、将来の生活設計に応じて早めの名義変更が大切です。
Q3. 弁護士に依頼するべきか?
特にモラハラやDV、不倫といった離婚理由が関係している場合、弁護士への相談が有効です。最近では、無料相談を行う法律事務所も増えており、24時間受付対応やメール相談に対応している事務所もあります。必要に応じて養育費や慰謝料の交渉、親権の調整まで一括して支援してくれるケースも多いです。
Q4. 契約者と被保険者が異なる場合はどうすればよいか?
例えば、「契約者=夫、被保険者=妻、死亡保険金受取人=夫」という場合、契約者を変更しなければ保険料の支払い義務は夫に残ったままです。契約者変更が可能な保険商品であれば、協議に基づいて新しい名義に変更しましょう。子どもがいる場合は、通常、契約者を親権者とし、受取人を子どもに設定することが多いです。
Q5. そもそも保険は解約したほうがいいの?
単純に「離婚したから解約」と考える必要はありません。保険の価値(解約返戻金)や今後のライフプランを考慮して判断すべきです。特に持病があるなど健康面で問題を抱える場合、新たに加入できないこともあります。保障が必要なら、次の保険に加入できたことを確認してから、元の契約を解約するようにしましょう。
Q6. 面会交流のある親が学資保険を払っていた場合は?
学資保険の契約者が面会交流中の親(非親権者)であっても、子どものために保険を継続するケースは多いのではないでしょうか。保険料の支払いや名義をどうするかは、協議・調停の場で条件を明確にしておきましょう。関係者間で公平な合意が得られるよう、一覧形式で保険の加入状況を整理しておくとスムーズです。
Q7. 保険以外に見直すべき関連制度は?
離婚に伴い、税法上の扶養控除や配偶者控除、自動車保険の契約者、共済や損害保険、住宅ローン、年金分割の手続きも必要になる場合があります。どれも「そのまま」にしておくと、後から「なぜ変更しなかったのか?」というトラブルに発展しかねません。夫婦間での協力や話し合いが必要です。
特に最近では自宅を購入する際、ペアローンを組んだ後の離婚でトラブルになるケースが増えています。詳しく知りたい方は次の記事を確認してください。
▶【関連記事】ペアローンを組んだ後に離婚したら問題に?!対処法を解説します
生命保険は離婚後の生活を考えて見直そう

貯蓄型の生命保険は、財産分与の対象になります。
離婚をする際は、様々な手続きが必要なことから生命保険についての手続きを後回しにして、忘れてしまうことも多いでしょう。
また、離婚することで一旦その契約自体をリセットしたくなり、解約してしまいたい気持ちも起こるかもしれません。
しかし、生命保険は万一の事があった際に、遺された家族が困らないように加入するものです。そして生命保険は、年齢が上がれば保険料が高くなり、体の状態が悪くなれば加入すること自体が難しくなります。
離婚時には、理性よりも感情が先に動いてしまいがちですが、生命保険については、離婚後の生活についてしっかりと考えた上で、冷静に判断することが大切です。
どうしたら良いか分からない場合は、ソナミラのコンシェルジュに相談してみてください。
離婚後のライフプランを立て、保険の見直しを一緒に検討することが可能です。オンラインで相談できますので、まずは一度利用してみてください。
【ここをクリック】財産分与で悩みを抱えているならアドバイスを受けてみませんか?ソナミラでFP相談してみよう
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!


 FP相談予約
FP相談予約








