貯蓄型保険はおすすめ?20代女性が選ぶメリットとデメリット
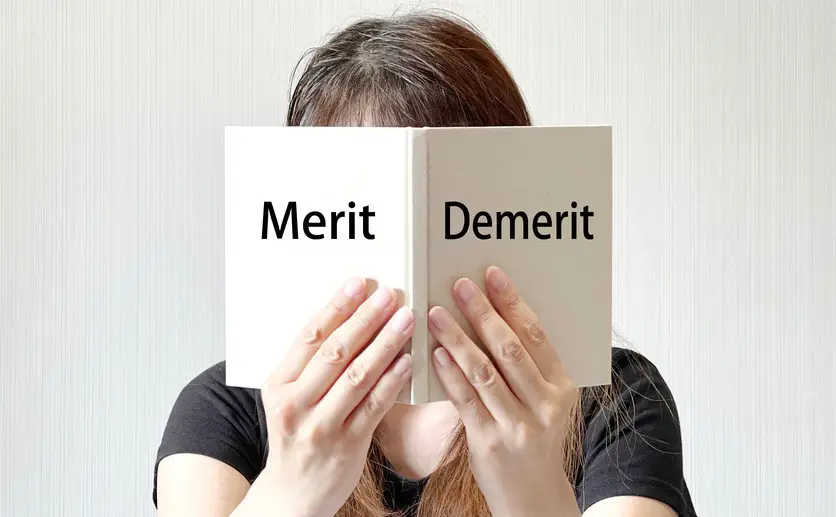
生命保険には大きく分けて、保障と貯蓄を兼ね備えた「貯蓄型」と、貯蓄性はないものの保険料が安い「掛け捨て型」の2種類の保険商品があります。20代は一般的に病気や死亡のリスクが小さく、また、公的保険制度である高額療養費制度もあります。高額療養費制度は、年齢や所得に応じて医療費の負担を軽くする国の制度です。
以上の理由から、生命保険に加入する必要性を感じないと考える方もいるかもしれません。本当に20代はそういったリスクが小さいのでしょうか?
結論から言うと、20代の女性こそ保険加入を検討する必要があります。
女性は20代半ば頃から、子宮頸がんなど女性特有の疾病(病気)にかかる確率が高くなるというデータが出ています。また、20代から貯蓄保険に加入することで将来必要になるお金を計画的に準備できます。
【ここをクリック】貯蓄型保険と掛け捨て型保険で悩んだ時はソナミラでFP相談してみよう
貯蓄型保険の知っておきたい基礎知識

まずは貯蓄型保険とはどういう生命保険で、どのような種類があるのか、また掛け捨て型の生命保険との違いや仕組み、保障内容をしっかり整理していきましょう。
貯蓄型保険とは?
貯蓄型保険とは、保険としての「保障」と、お金をためる「貯蓄」の2つの機能を兼ね備えた保険商品です。
貯蓄型保険には大きく分けて「養老保険」と「終身保険」の2種類があります。契約者から預かった保険料の一部を積み立てて、養老保険は満期時に満期保険金として、終身保険は解約時に解約返戻金としてお金を受け取ることができる、という特徴があります。
保障としては基本的に死亡時、保険金を受け取る保険であることは共通しており、違いは以下の通りです。
- 養老保険
10年間、60歳までなど、保障する保険期間が定まっている保険。満期まで生存していると満期保険金を受け取れます。保険期間内に死亡した場合は死亡保険金、高度障害状態になった場合は高度障害保険金が満期保険金と同額支払われるのが一般的です。満期になる前に途中解約した場合、解約返戻金(詳細は後述)を受け取れます。 - 終身保険
期間の定めなく保障が一生(終身)続く保険。死亡した場合は死亡保険金、高度障害状態になった場合は高度障害保険金が支払われます。解約すると解約返戻金を受け取れます。解約返戻金は一定期間を過ぎると、支払った保険料(払込保険料)よりも多くなることがあります。
掛け捨て型保険との違いは?
一方、掛け捨て型保険は「保障」に特化した保険商品です。貯蓄機能はありません。支払った保険料から積み立てしないため、保険期間中に解約をしても解約返戻金は受け取れません。解約返戻金があってもごくわずかです。
また、満期のある保険(保障期間が終身ではなく一定期間)であっても、一般的に満期保険金は受け取れません。
貯蓄型保険と掛け捨て型保険の保険料を比較すると、掛け捨て型保険の方が支払う保険料は比較的安くなります。
その理由は仕組みの違いです。貯蓄型保険は支払う保険料の中に積み立てるお金が含まれています。積立額が原資となり、満期時に満期保険金、解約時に解約返戻金を受け取ることができます。
一方、掛け捨て型保険は貯蓄性がなく、解約してもお金は戻ってきません。
貯蓄型保険と掛け捨て型保険はよく比較されますが、そもそも保険の種類が異なります。それぞれに、どういった種類の保険があるのかを解説していきます。
掛け捨て型保険には、以下のような種類があります。
- 定期保険
一定の期間、安い保険料で比較的高額な保障をもつことができる。 - 医療保険
病気やけがなどで入院や手術をしたときに、一定額の給付金が受け取れる。特約を付けることで先進医療にかかる費用も保障される。基本保障(入院・手術)に加えて三大疾病(がん・脳血管疾患・心疾患など)、女性特有の病気、通院保障などを特約で追加でき、保障の選択肢が広い。 - がん保険
がんに特化した保険で、がんに罹患する(かかる)と一時金や治療給付金、入院給付金・手術給付金・通院給付金などを受け取れる。がん専用の先進医療特約もある。 - 介護保険
所定の要介護状態になるか、公的介護保険制度の認定を受けた場合、保険金が受け取れる。
掛け捨て型保険には他にもたくさんの種類がありますが、共通するのは「基本的に満期保険金・解約返戻金がない」ということです。
貯蓄型保険の種類
■保険の種類:終身保険
概要
- 一生涯保障が続く保険
- 貯蓄機能がある
- 変額保険や外貨建てで運用し、資産形成に役立つ商品もある
一般的な保障範囲
- 死亡保障
- 高度障害保障
- 入院や通院などに備えた医療保障を付加できるケースがある
- 運用商品に保障機能もたせながら資産運用やインフレ対応ができる
保険期間
- 終身(⼀⽣涯の保障)
■保険の種類:学資保険
概要
- 子どもの教育をサポートする保険
- 解約しない限り目標額が受け取れる
- 満期までの一定期間、契約者に万が一のことがあっても保障がある
一般的な保障範囲
- 教育資金の準備
- 契約者(保護者)に万が一のことがあったときに保険料が払込免除となる
- 子どもの医療保障や死亡保障が付加できるケースがある
保険期間
- 定期(一定期間の保障)
■保険の種類:養老保険
概要
- 老後に備える保険
- 満期保険金が受け取れる
- 老後の生活費やマイホーム購入資金、将来の教育資金として貯蓄できる
- 満期までの一定期間、保障がある
一般的な保障範囲
- 死亡保障
- 入院やケガなどに備えた医療保障が付加できるケースがある
- 満期金は契約時点で確定しているので資金計画が立てやすい
保険期間
- 定期(一定期間の保障)
■保険の種類:個人年金保険
概要
- 老後の生活資金を準備する保険(公的年金の上乗せ)
- 定めた年齢から年金を受け取れる
- 変額保険や外貨建てで運用し、資産形成に役立つ商品もある
一般的な保障範囲
- 死亡保障
- 入院やケガなどに備えた医療保障が付加できるケースがある
- 契約時点で将来の受取額が確定している(運用商品以外)
- 運用商品はインフレ対応や資産運用ができる
保険期間
- 定期(一定期間の保障)
貯蓄型と掛け捨て型の違いを、より詳細に知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
▶【関連記事】生命保険には「貯蓄型」と「掛け捨て型」がある?知っておこう3つの基本形
貯蓄型保険を20代女性が選ぶメリデメ
貯蓄型保険に加入することで、将来必要となるお金を計画的に準備できます。また、20代女性はそれまでと比べ、特定の病気にかかるリスクが上昇することから、早めにリスクに備える必要があります。詳しく見ていきましょう。
● メリット
貯蓄型保険の最大のメリットは、保険と貯蓄の両立ができるという点です。
貯蓄型保険は支払う保険料の一部を保障のためだけではなく、満期時や解約時にお金が受け取れるように積み立てる仕組みになっています。
20代の今は必要がなかったとしても、将来必要になることが予想される子どもの教育資金や老後資金などを計画的に準備できます。
生命保険文化センターによると、25歳女性の死亡率は0.026%、55歳は0.213%、75歳は1.219%。そして入院数(人口10万人あたり)は25~29歳で約0.26%、55歳~59歳で約0.55%、75~79歳で約2%と、年齢が上がるごとに死亡・入院のリスクが高くなっています。
また、厚生労働省の調べでは、生涯に支払う医療費の53%は70歳以上に支払うという結果が出ています。
これらのデータから、20代女性は病気や死亡のリスクが低いため、医療保険や死亡保険の保険料が低く設定されていると言えます。
貯蓄型保険のなかでも終身保険や個人年金保険などは、保険料を払い込む期間が長ければ長いほど、少ない保険料で解約返戻金や年金受取金額を多く受け取ることができます。つまり、年齢が若い時に貯蓄型保険に加入すると安い支払保険料で契約できるということです。
20代女性は病気や死亡のリスクが小さいのに、保険に入る必要があるのかと思われるかもしれません。しかし、今は20代でも、50〜70代に年齢を重ねれば、前述のデータのように病気や死亡のリスクは高まります。女性は、20代から女性特有の病気にかかるリスクが高くなるとお伝えしました。そのため、20代のうちから安い保険料で一生涯保障が続き、貯蓄性のある終身保険や終身医療保険に加入しておくことはリスクを軽減させる一つの手段と言えるでしょう。
また、貯蓄型保険に加入しておくことで、子どもの教育費や住宅ローンの頭金をはじめ、資金が必要になった際に保険を解約して解約返戻金を活用できます。
● デメリット
お伝えしてきたように貯蓄型保険にはたくさんのメリットがありますが、保障と貯蓄を兼ね備えた保険であり、掛け捨て型保険よりも保険料が高額になるという特徴があります。20代で働き始めて数年は、収入に余裕のないことが多く、貯蓄型保険のために支払う保険料が生活を圧迫する可能性があります。貯蓄型保険に加入する場合は、ご自身の生活スタイルや加入目的をしっかりと検討する必要があります。
そして貯蓄型保険は加入時の保障内容が長期間続く保険です。そのため、時が経つにつれ保障内容が生活スタイルに合わなくなることが考えられます。
20代から30代はライフステージの変化が大きい年代です。20代で「これがベストだ」と思って加入した保険でも、数年後に結婚や出産、転職、住宅購入などのイベントが発生することにより保険に対するニーズが変化する可能性があります。
常に、加入している保険のメンテナンスが必要です。ファッションやお肌のお手入れと同じように、そのときの自分に適切な保険に見直していくことが大切です。
ただし、現在加入している保険の見直しや解約をするには注意が必要です。商品にもよりますが、一定期間内に解約をすると解約の手数料(解約控除)を引かれる保険商品もあります。また、見直しをする際は、最初に加入した時よりも年齢が上がっていることがほとんどだと思います。保険は年齢が上がると保険料も上がるケースが多くなります。加入時・見直し時にはその保険が自分にとって本当に必要な内容なのかを見極めていかなければいけません。
加入する時も見直しをする時も、どの時期にどのくらいのお金が必要なのか、自分に必要な保障は何で、いくら必要なのか。こういったライフプランを立てたうえで保険選びをしていくことが重要です。
しかし、保険の基礎知識がなく、どこに相談したらいいのか分からない、ということもあるでしょう。
保険は「保険代理店」等で相談できます。多くの保険代理店では、無料相談が行われています。さまざまな特徴のある保険代理店がありますが、保険代理店を選ぶ上での判断基準例として、下記のようなものがあります。
- 取扱保険会社数が多い。
- 生命保険(死亡保険・医療保険・就業不能保険・がん保険など)と損害保険(火災保険・自動車保険など)の両方を取り扱っている。
- 専門知識(FP技能士・CFP・AFPど)を持った担当者に相談できる。
- 保険商品の提供だけでなく、お金や健康に関する情報提供のサービスが利用できる。
保険は「金融商品」であり、自分に合った商品を選ぶのは難しいものです。そのため、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するなど、専門家の意見を取り入れることで希望に沿った保険選びができます。
【ここをクリック】自分に合った商品を探すなら!ソナミラでFP相談してみよう
貯蓄型保険を20代女性が選ぶポイント

20代女性が自分に合った貯蓄型保険を選ぶときのポイントとして、必ず知っておいてほしい「解約返戻金」について解説していきます。
貯蓄型保険の特徴を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
▶【関連記事】保険の種類と特徴を徹底解説!初心者でもわかりやすく!
解約返戻金の返戻率を確認する
解約返戻金(解約払戻金)の返戻率とは、支払った保険料の総額に対し、解約した時に戻ってくる金額の割合(リターン)を指します。
たとえば、契約している保険を解約したとします。解約するまでに支払った保険料総額が100万円、解約して戻ってきたのが110万円とすると、110万円÷100万円で解約返戻率は110%と計算されます。
戻ってくる金額の詳細は、保険会社や保険商品、契約した時期によって変わります。
解約返戻率が高いということは、解約したときに受け取る金額が大きくなることを意味します。
たとえば、前述の例で、解約したときに戻ってきたお金が80万円だった場合、80万円÷100万円で解約返戻率は80%ということになります。この状態を一般的に「元本割れする」と表現されます。
そして、解約返戻率が100%というのは、支払った保険料と解約時に戻ってくる金額が同じだということを意味します。
保険料を安く抑えたいときは低解約返戻金型か無解約返戻金型
また、貯蓄型保険には「低解約返戻金型」「無解約返戻金型」という商品もあります。
貯蓄型保険は、契約時に保険料を支払う期間(たとえば10年間、60歳まで、一生涯など)を決めます。この期間を保険料払込期間と呼びますが、低解約返戻金タイプは通常よりも保険料払込期間中の解約返戻率を低く設定し、保険料を割安にしています。
無解約返戻金タイプは、文字通り解約返戻金のない保険商品です。解約返戻金がある保険商品よりも保険料が安くなります。
自身に合った保険を選ぶ
貯蓄型保険は保障と貯蓄を兼ね備えた保険ですが、たくさん貯蓄をしたいと考えて高額な保険料で契約をしてしまうと、毎月の生活費に使えるお金が足りなくなり、生活を圧迫してしまいます。ご自身が希望するライフスタイルを確認し、どのくらいの保険料であれば家計の負担にならないのかを検討しましょう。
20代から30代はライフスタイルが大きく変化する年代だとお伝えしました。そんな年代にはどのようなリスクが潜んでいるのでしょうか。
たとえば、20代から30代の女性であれば、結婚・妊娠・出産などをする方、独身で人生を謳歌する方、自宅を購入する方など多種多様な人生の選択肢、出来事があります。
そのなかで、妊娠出産時のリスクとして切迫流産・切迫早産、異常分娩(帝王切開など)による入院・手術や、病気やけがなどで働けなくなり、収入が減少してしまうことも考えられます。
そして、女性特有の病気の罹患率が高くなる年代でもあります。国立がん研究センターによると、20代半ばからは子宮頸がん、30代半ばからは乳がんの罹患率が高くなるというデータがあります。
どのようなライフスタイルを選ぶにせよ、こういったことを踏まえて、女性特有の疾病(病気)を保障する女性保険も検討しておくと安心です。
貯蓄型保険を上手に選ぶためのQ&A

貯蓄型保険を選ぶ際、「ネットやサイトで見かけた情報が本当に正しいだろうか」「保険会社の商品をどう比較するべきなのか」など、悩む点や気になる点は多いのではないでしょうか。
ここでは、よく寄せられる疑問に最新の情報を踏まえてお答えします。
Q1. 貯蓄型保険を選ぶうえで「給付金」や「保障内容」はどのように比較すべき?
給付金の金額や支払い条件、保障内容、保険期間などは商品によって大きく異なります。保険会社のホームページや公式サイトを確認し、具体的に「どのタイミングで、どの条件で、どれくらいの給付が受けられるのか」をチェックしましょう。サイト内の比較表やQ&Aページも活用するのがおすすめです。
Q2. 保険契約を途中で解約した場合、「解約返戻金」はどうなる?
契約内容に基づいて、一定期間を過ぎれば十分な解約返戻金が受け取れる商品もあります。ただし、契約から間もないうちに解約すると、解約返戻率が低く、元本割れになるケースも多いため注意が必要です。解約時の返戻金の条件は事前に確認しておきましょう。
Q3. 加入後にライフスタイルが変わったら、どう対応すればいい?
妊娠・出産・転職・引越しなどのライフイベントにより、当初の保険がライフスタイルに合わなくなることがあります。そんなときは、保険契約の内容を確認し、必要に応じて見直しや追加契約を検討しましょう。保障内容や保険料の変更が可能かどうかは、契約している保険会社のコールセンターに問い合わせることでも確認できます。
Q4. 複数の保険商品を比較する上でおすすめの方法は?
保険商品ごとの内容や保険料を比較するには、総合保険情報サイトや保険代理店が提供するシミュレーションツールの活用が効果的です。保障内容・保険期間・返戻金の有無などを一覧で比較できるため、全体像をつかみやすくなります。ただし、保険には商品によって独自の条件や特約があるため、単純な価格比較だけではなく内容の違いにも注意を払いましょう。
Q5. どのような人に貯蓄型保険は向いている?
安定した収入のある業務に従事していて、かつ将来の教育資金や老後の生活資金に備えて、計画的に資産形成を行いたい方に向いています。20代のうちに加入しておくことで、保険料が割安になり、長く継続することで魅力的な返戻率が得やすくなります。また、将来的な不確実性や医療費負担に備える手段としても有効です。
Q6. 保険のプロに無料相談するメリットは?
生命保険は専門性の高い商品であるため、自分に最適な保険を見つけるには難しさがあります。そんなときは、ファイナンシャルプランナー(FP)や保険代理店の無料相談サービスを活用するのがおすすめです。
FPに相談すれば、今後のライフプランやリスクを踏まえた適切な保障内容を提案してもらえます。また、円建ての保険商品に加え、外貨建てや変額型など多様な選択肢についてもアドバイスが受けられます。
保険代理店であれば、無料相談可能な窓口も多いため、気軽に利用し、納得のいく保険選びを進めていきましょう。
貯蓄型保険は20代女性におすすめ

20代は一般的に病気や死亡のリスクが小さいと言われています。しかし女性特有の病気は20代からリスクが高くなるため、健康状態に問題がないうちに将来の病気に備えた保険に加入する必要性があるといえます。そして、安い保険料で加入できる貯蓄型の保険に20代から加入しておくと、将来のお金の備えとなります。
ただし、保険は複雑な商品です。保険選びをするときには専門家に相談することをおすすめします。近頃はインターネットで資料請求をして申し込みもご自身で簡単にできますが、注意事項や保険のルールブックである約款の内容をしっかり理解することは簡単ではありません。
前述した通り、保険は「金融商品」です。適切な保険商品選びは難易度が高いもの。そのため、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するなど、専門家の意見を取り入れることで希望に沿った保険選びができます。
一つの商品で万人のリスクをカバーすることはできません。それぞれのお客さまに合った商品を提案できるように、ソナミラでは複数の生命保険会社の商品を取り扱っています。
自分のことは自分が一番分かっていると思うかもしれません。あなたはあなた自身の専門家ですが、あなたが気づいていないことがあるかもしれません。そこで、保険の専門家に話を聞いてみませんか?ソナミラのコンシェルジュは、あなたの困りごと・悩みごとの本質を見極めて、それが保険商品で解決できるのかを一緒に考えていきます。誰にでも合うプランではなく、あなたに合ったプランを提案します。
保険商品を提案するということは、お客さまの人生そのものに関わるということです。そこには保険はもちろん、家計や資産形成、相続などのマネープランも関わってきます。保険商品だけではなく、必要に応じて投資信託などの金融商品もご案内しています。お客さまとご家族に関わるライフプラン全般についてのご相談が可能です。
ご相談は無料。店舗もしくはオンラインで相談できます。
【ここをクリック】あなたの困りごと・悩みごとをお聞きします!ソナミラでFP相談してみよう
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考
高額療養費制度について
出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
0歳の男女各1,000人の年齢別死亡者数と平均余命
出典:生命保険文化センター「0歳の男女各1,000人の年齢別死亡者数と平均余命」
病気やケガで入院する確率
出典:生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」
生涯に支払う医療費
出典:厚生労働省 医療保険に関する基礎資料 2.3 統計表一覧 年次報告 「令和2年度(令和5年1月)」
子宮頸がんの罹患率
出典:国立がん研究センター がん情報サービス
乳がんの罹患率
出典:国立がん研究センター がん情報サービス

 FP相談予約
FP相談予約








