「がん保険に入っておけばよかった」となぜ後悔するのか?|知っておきたい知識とは

現在は、2人に1人以上ががんになる時代です。がんに罹患すると、入院や手術、通院治療などで高額な医療費がかかる可能性が考えられます。
がんの医療費負担をカバーするために、がん保険への加入を検討している方も多いのではないでしょうか。がんに罹患したあとに「がん保険に入っておけばよかった」と後悔しないためにも、保険に関する情報を集めることは大切です。
本記事では「がん保険に入っておけばよかった」と後悔する人の特徴や、がんの治療で必要となる治療費などを解説します。
【ここをクリック】後悔する前にアドバイスを受けてみませんか?ソナミラでFP相談してみよう
がん保険に入っておけばよかった

がん保険に入っていない状態でがんに罹患すると、さまざまな理由から「がん保険に入っておけばよかった」と後悔する可能性があります。
具体的に、どのようなケースが考えられるのか解説します。
治療費を払う金銭的余裕がなく希望する治療がうけられなかった方
がんの治療を受ける際に十分な貯金がないと、経済的な理由から自身が希望する治療を受けられない場合があります。がんの治療法にはいくつか種類があり、すべてのがん治療が公的医療保険制度の対象ではありません。
例えば、先進医療の技術代は公的医療保険適用外で、全額自己負担 (※)となります。
(※)中央社会保険医療協議会「令和6年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」によると、がんの治療で用いられる陽子線治療の1件当たりの技術料平均額は2,679,335円でした。
ほかにも、入院時の差額ベッド代(個室、もしくは定員人数が少ない部屋を利用する場合)・食事代や医療用ウィッグ、病院への交通費などの出費は公的医療保険において全額自己負担です。また、がんは再発や転移の可能性があり、入院するたびに治療費だけでなく差額ベッド代の支払いが必要となります。
がんは長期にわたる治療が必要な場合が多く、治療費の総額がほかの病気と比べて高額になりやすいことから「家計への負担が想像以上に重く、がん保険に入っておけばよかった」と感じることもあるでしょう。
自由診療について知りたい方は次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】がんの自由診療とは何?がん保険を検討する前に知っておきたいこと
がん治療に伴い家族に負担をかけてしまうおそれのある方
がんの治療に伴って、家族に負担をかけてしまうケースも考えられます。現役で働いているときにがんに罹患すると、症状によっては療養で仕事を休む必要が出てきます。
健康保険の被保険者である会社員が長期療養した場合、最長で1年6か月間は健康保険の傷病手当金が支給されるとはいえ、支給額は標準報酬月額約3分の2です。収入が減ってしまうことから、家族の生活に悪影響が出てしまうおそれがあります。
がんの治療が長引けば収入が減る期間も長くなります。場合によっては、子どもの進学資金や老後資金のために貯蓄を取り崩す必要に迫られる可能性も考えられるでしょう。その結果、子供が希望している進学をかなえられなかったり、老後資金が心もとなくなったりするリスクがあります。
このように、長期の休職や就業不能により、住宅ローンの支払いや子ども教育資金準備など、ライフプランニングに支障をきたす可能性がある場合は、早い段階で検討することが得策です。
経済的な負担だけでなく、通院の付き添いの手間や体調面を気にかけることに伴う心労など、精神的な負担をかけてしまうおそれもあります。抗がん剤を服用すると、嘔吐やしびれ、脱毛、強い倦怠感などの副作用が伴うことが多く、家族に心配をかける場面が増えがちです。
このように、がんは本人だけでなく、家族にも経済的・精神的な影響を及ぼす点も見逃せません。
がん治療後の保険加入が難しい方
がん保険に入ろうと思っても、保険会社の審査に落ちてがん保険に加入できないケースがあります。がん保険に加入していない状態で一度がんに罹患すると、がん保険に入りたくても入れないという状況になりかねません。
がん保険は加入時に健康状態の告知を必要とするのが一般的で、必ず加入できるとは限りません。がんに罹患した方でも加入できる「引受基準緩和型」のがん保険がありますが、一般的な保険よりも、比較的保険料が高く設定されているというデメリットがあります。
このように、自分に保険が必要になったとしても、必ずしも入りたいがん保険に入れるとは限らない点には注意しましょう。
がん保険に加入できない場合の対処法について、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【関連記事】がん保険に入れない人はどうしたら良い?加入できないケースと対処法
後悔する前に知っておきたい知識

がん保険に加入する前に、がんに関するデータを確認しましょう。以下で、がん保険の加入率やがんの治療費の目安などを解説します。
がん保険で後悔したことについて、こちらの記事でまとめています。
▶【関連記事】がん保険で後悔したことは?加入の必要性や入っていないリスク
日本人の死因で最も多いのはがん
厚生労働省の資料によると、令和6年における日本人の死因で最も多かったのはがん(悪性新生物)でした。日本全体の死亡者数の23.9%を占めており、4.2人に1人ががんで亡くなっていることがわかります。
令和6年は、38万4099人ががん(悪性新生物)で亡くなっています。がんは全員が罹患するわけではありませんが、多くの方が命を落とす病気である点に留意する必要があるでしょう。
がん保険の加入率は?
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、令和4年におけるがん保険・がん特約の加入率は39.1%でした。約4割の方が、保険でがんに備えていることがわかります。
男女とも40歳代の加入率が最も高く、女性は半分を超え、男性も46.4%に達しています。20代の方でも男性が14%、女性が21.9%、30代の方でも男女ともに4割以上が加入しています。
一般的に、がんの罹患率は年齢が上がるほど上昇します。しかし、一度がんに罹患すると自分が希望しているがん保険に加入できない可能性が高まることから、20代や30代から加入する人も一定数いると考えられます。
がんの治療費は?
全日本病院協会によると、公的医療保険適用前のがんに関する1入院あたり治療費平均額(2023年度 年間集計)は以下のとおりです。
- 胃のがん:994,478円
- 結腸のがん:906,668円
- 直腸のがん:1,096,120円
- 気管支および肺のがん:892,949円
自己負担割合を3割とした場合、公的医療保険適用後の自己負担額はおおむね30万~40万円と計算されます。また、健康保険制度には「高額療養費制度」があるため、一般的な月収(標準報酬月額28万~50万円)の方は毎月の治療費を8万~10万円程度に抑えられます(高額療養費制度の自己負担上限額は年齢や所得により異なります)。
しかし、がん治療のすべてが公的制度に含まれるとは限りません。開発中の試験的な治療法や薬、医療機器を使った治療や、重粒子線治療や陽子線治療といった先進医療の技術料は全額自己負担 (※)です。
ほかにも、手術後の入院で個室や人数の少ない部屋を希望する場合は差額ベッド代が発生します。例えば、差額ベッド代が1泊1万円だと仮定し、10日間入院すると10万円が自己負担額となります。
がん保険を検討するタイミングは?
がん保険への加入は、早い段階での検討が重要です。というのも、がん保険には多くの場合、90日間の免責期間が設けられており、契約した直後にがんに罹患しても、すぐに給付金がもらえるわけではありません。この免責期間中にがんと診断された場合、保険金の支払対象外となってしまうため、発症前の“備え”が欠かせません。
また、がんは発症後に治療が長引く傾向があり、早期発見できたとしても放射線治療や抗がん剤治療など、長期の通院が必要となるケースもあります。こうした通院治療を保障する保険に早めに加入しておくことで、休職中の支出や交通費の負担などを軽減できます。
さらに、加入時には健康状態の告知が求められます。もしも持病がある場合や、がんと診断された経験がある場合は、保険への加入が難しくなる、あるいは引受基準緩和型のような保障範囲が限られた保険商品しか選べない場合もあります。これらは一般的に保険料が高く設定されており、費用対効果のバランスも検討が必要です。
特に40代・50代・60代はがんの罹患率が急増する年代であり、加入を検討するには適したタイミングといえます。70歳を超えると、加入できる商品が限られてしまうこともあるため、ライフプランに合わせて最適なプランを早めに見つけておくことが大切です。
がん保険の選び方と年代別のポイントはこちらでまとめています。
▶【関連記事】後悔しないがん保険の選び方は?基礎知識と年代別のポイント
がん保険の免責期間について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
▶【関連記事】免責期間なしのがん保険ってあるの?メリットとデメリットを解説
【ここをクリック】がん保険に加入する必要があるかどうかをソナミラでFP相談してみよう
がん保険で受けられる保障内容は?

がん保険の種類によって、保障内容は異なります。受け取れる給付金の種類やタイミングが異なるため、加入前に保障内容の確認は欠かせません。
以下で、がん保険に加入することで受けられる主な保障内容を解説します。自分と家族が安心して生活するためにも、給付金の内容や所定の受け取り条件をチェックしましょう。
診断給付金
診断給付金とは、がんと診断された際に受け取れる給付金です。一時金で受け取れるケースがほとんどで、がんの治療に備えるための費用や、当面の生活費に充てられます。
受け取り回数が1回のみの保険商品と、複数回にわたって受け取れる保険商品があります。複数回受け取れるがん保険でも「1年につき1回まで」など、一定の条件が設定されているケースが多く見られます。
がん入院給付金
がん入院給付金とは、がんの治療で入院した際に、入院日数に応じて支払われる給付金です。保険加入時に入院日額や受け取り可能な上限日数を決め、契約内容に基づいて給付金を受け取れます。
「1日当たり〇円」のような形で受け取り、保険商品によっては日帰り入院から保障されます。
がん通院給付金
がん通院給付金とは、がんの治療で通院した際に受け取れる給付金です。がん治療で入院したあとの通院のみを保障対象としている商品や、がん治療で入院をする期間前後の通院を保障対象としている商品があります。
たとえば、放射線治療は多くの場合、入院せずに通院治療で行われるのが一般的です。週に複数回の通院が数週間続くケースもあり、交通費や付き添いなどの負担も発生します。そのため、通院をカバーする保障があると安心です。
通院給付金は、基本保障の内容に含まれているケースと、特約として付加することで受け取れるケースに分かれます。また、退院時に一時金として支給されるタイプもあるため、加入前に受け取り条件を確認しておくとよいでしょう。
がん手術給付金
がん手術給付金とは、がんの手術を受けたときに受け取れる給付金です。給付金額は「がん入院給付金日額の10倍~40倍」といった形で設定されているケースが多く、中には給付金を具体的な額に設定している保険もあります。
手術を受けるたびに給付金を受け取ることができ、受け取りの上限回数は設けられていないのが一般的です。
先進医療給付金
先進医療給付金とは、先進医療を受けたときに受け取れる給付金です。先進医療は技術料が全額自己負担となりますが (※)、先進医療給付金が付いたがん保険に加入すれば経済的負担を軽減できます。
受け取れる保険金額は「自己負担と同額(通算2,000万円まで)」といったように設定されているケースが一般的です。
※「先進医療に係る費用」は全額自己負担ですが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用には健康保険が適用されます。
がん死亡給付金
がん死亡給付金とは、がんで亡くなった場合に遺族が受け取れる給付金です。がん保険によっては、がん以外の原因で死亡した場合でも給付金を受け取れます。
給付金額は「がん入院給付金日額の10倍~100倍」といったように設定されるケースが一般的です。
生存給付金
生存給付金とは、特定の期間生存していることで受け取れる給付金です。保険によっては「祝い金」という文言を用いています。
生存給付金の受け取れる条件は、保険会社によって異なります。また、保険会社によっては生存給付金を受け取らず、保険期間満了まで保険会社に預けられるがん保険があります。
がん保険の選び方と後悔しない見直し
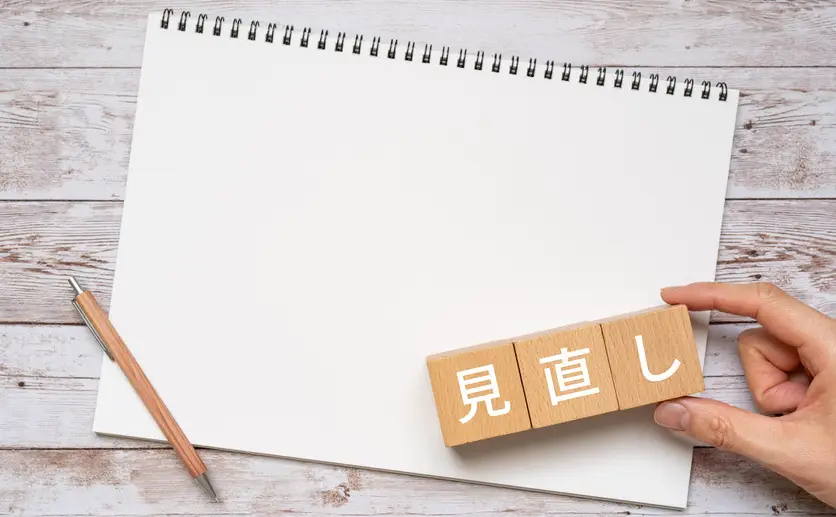
がん保険に加入したものの「思ったより保障が手薄だった」「給付の条件が厳しくて請求できなかった」と感じる人もいます。保険商品は時代やニーズに応じて進化しており、特に2025年以降は「通院治療への対応」や「長引いた治療費の補てん」に焦点を当てた保険も増えてきました。
ここでは、後悔しないために重要なポイントを整理して紹介します。
今のライフスタイルに合った保険か見直そう
先述したとおり、がん治療の実態は日々変化しています。特に近年では、入院ではなく通院を中心とした治療スタイルが主流です。そのため、「入院給付金だけではカバーしきれなかった」という声もあります。通院給付金や先進医療特約など、医療技術の進化に対応した保障を選ぶことが重要です。
また、若い世代や共働き世帯にとっては「働けない期間の生活保障」がより重要になるため、「就業不能保険」や「終身保障タイプ」の選択肢も検討の価値があります。総合的に自分に必要な保障を見極めましょう。
定期型か終身型か?目的別に選ぶ
がん保険には大きく分けて「定期型」と「終身型」があります。子育て中や教育費がかかる世帯には、保険料を抑えた定期型が向いています。一方、年齢を重ねてからの発症リスクに備えるなら、解約返戻金がある終身型を選ぶ人もいます。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、「将来に向けてどれくらいの保障が必要なのか」「いくらまで保険料をかけられるのか」といった点をしっかり考えることが後悔しない選び方の第一歩です。
保険に付属のサービスも確認をしよう
がん保険の契約前に確認したいのが、保険会社の「請求対応」です。万が一のとき、スムーズに給付金請求ができなければ意味がありません。インターネット上の口コミや比較サイト、セミナーなどで保険会社の実際の対応事例や顧客満足度をチェックするのもおすすめです。
また、保険会社によっては「サポート専任スタッフ」が在籍しており、患者や家族向けの相談サービスが充実しているところもあります。こうした“付加価値”の部分も選択肢として検討しましょう。
見直しのタイミングはライフイベントごとに
がん保険は、一度加入して終わりではなく、ライフスタイルの変化や家族構成の変化に応じて見直すことが大切です。たとえば、結婚・出産・住宅購入・退職などの節目では「必要な保障の内容」や「保険料の負担感」も変わります。
特に高額な保障をつけすぎて「不要な部分に保険料がかかっていた」と感じる人もいれば、「見直しを後回しにしていたら制限が多くなった」というケースも。保険の“定期健診”として、3~5年ごとに保険の内容を確認することをおすすめします。
若い世代ががん保険に入る意味は?
近年、アメリカでは若年層(15〜39歳)におけるがんの罹患率が上昇傾向にあるともいわれています。シカゴ大学医療センターの研究によると「若年性がん(early-onset cancer)」が増加中とされ、2019年から2030年にかけて、早期発症がんは30%増加すると予測されています。
また、ハーバード公衆衛生大学院によると、がんの罹患者数増加の背景に肥満、加工食品中心の食生活、運動不足といった生活習慣が大きく影響していると報告されており、炎症ががんにつながるメカニズムとの関連も示唆されています。
さらに、ミレニアル世代(1980–1990年生まれ)では、虫垂がんの発症率が約4倍に急増しており、環境や生活習慣がリスクに寄与している可能性があります。女性特有のがんに関しても、30代から乳がんや子宮頸がんの発症が増加傾向にあり、早期発見と備えが重要です。
このような状況を踏まえると、若い世代が「まだ若いから大丈夫」と思って放置していると、後からがん保険に加入しようとしても告知制限に引っかかる可能性があります。早めの加入と備えが、経済的・身体的にも安心につながります。
自営業者ががんに備えるべき理由
自営業者やフリーランスの方にとって、がんによる就業不能は収入の断絶を意味します。会社員と異なり、傷病手当金などの制度の対象外であるケースも多いため、がんに罹患した場合の経済的リスクは非常に高いといえます。
そのため、「保障が手厚い」もしくは「収入保障がある」タイプの終身型がん保険や働けなくなっても給料が補償される所得補償保険を選択するのがおすすめです。
また、法人経営者としての経費化の活用を見据えるなら、法人契約型のがん保険も候補に挙がってきます。ファイナンシャルプランナーや保険代理店に相談して、慎重に保険設計していきましょう。
さらに、働き続けられない期間に起きる家族への影響(教育費・住宅ローンなど)も大きいため、「見直しのタイミング」や「サポート体制の充実」についても意識して保険選びをすることが大切です。
がん保険で後悔しないためのQ&A

がん保険を検討している方の中には、「本当に入ったほうがいいのか?」「どの保険が自分に合っているのか?」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、がん保険に関してよく寄せられる質問をQ&A形式で一覧にまとめました。加入前のチェックポイントとしてご活用ください。
Q1. がん保険に入らなくても、医療保険でカバーできるのでは?
確かに医療保険でも入院費や手術費はある程度カバーできますが、「がん」に特化した保障があるのががん保険の強みです。たとえば、診断給付金や先進医療給付金など、がんならではの支出に対応するものはがん保険でしか受けられないことが多く、治療にかかり始めた段階から活用できます。
Q2. がん保険と医療保険、どうやって選べばいいの?
保険選びの方法としては、まず現在加入している保険の保障内容を確認し、「がんに備える保障があるかどうか」をチェックすることが基本です。そのうえで、総合的な保障(医療・がん・就業不能など)を希望する場合は、特約の付加や複数商品の組み合わせも検討しましょう。最近では、生命保険とがん保険をセットにしたプランも登場しています。
Q3. がん保険に入っても、実際に給付金が出ないことがあると聞きました
「がん」と診断されたのに給付されないケースの多くは、「免責期間中の発症」や「保障対象外の疾病」によるものです。保険に加入する際は「保障開始時期」「対象となるがんの定義」などの特記事項をしっかり確認しましょう。「あとで知っても遅い…」ということにならないように、契約前にまとまった情報を比較するのがポイントです。
Q4. 若いうちからがん保険に入るのはもったいないのでは?
「がんは高齢者の病気」というイメージがありますが、実は30代・40代の働き盛り世代でも罹患するケースもあります。年齢が若いうちに加入すれば保険料を抑えやすく、マネー効率化の観点でも有効です。特に第1子の誕生や住宅購入のタイミングなど、「備えどき」と感じるあたりで積極的に見直しを検討するとよいでしょう。
Q5. 介護や老後に備える保険とがん保険は両立できる?
近年では介護保険や認知症保険などのニーズも高まっていますが、がん保険と併用して設計することは十分可能です。保険設計を総合的に考えるには、保険のプロに相談し、「どの保障を、どこまで重ねるか」を整理するのがおすすめです。がんにかかった際、治療と並行して介護が必要となる例もあるため、他の保障とのバランスが大切です。
がん保険で後悔する前に相談しよう

がん保険に加入しようとしても、健康状態や既往歴によっては希望しているがん保険に加入できないことも起こり得ます。がん保険に未加入の状態でがんに罹患すると、自分や家族に経済的・精神的負担を強いてしまい「がん保険に入っておけばよかった」と後悔することになりかねません。
がんに罹患すると、入院費用や手術費用などで治療費がかさみがちです。がんに対する経済的な備えが欲しい方は、がん保険への加入を検討したほうがよいでしょう。
もし迷ったときは、ファイナンシャルプランナーや保険のプロに相談することで、最適な保険選びの提案を受けることができます。
がん保険に加入すべきか迷っている方や、自分にがん保険が必要かどうか判断できない悩みを抱えている方は、ソナミラのコンシェルジュへ相談してみてはいかがでしょうか。
ソナミラでは店舗もしくはオンラインで無料の保険相談を行っており、保険の選び方や将来のライフプランも含めて専門家に相談できます。
【ここをクリック】がん保険選びで迷ったらソナミラでFP相談してみよう
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考
2人に1人以上ががんになる時代
出典:国立がん研究センター 最新がん統計
がんの治療で用いられる陽子線治療の1件当たりの技術料平均額
出典:公益財団法人 生命保険文化センター 先進医療とは?どれくらい費用がかかる?
支給額は標準報酬月額約3分の2
出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
抗がん剤の副作用
出典:国立がん研究センター
日本人の死因
出典:厚生労働省 令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況
がん保険・がん特約の加入率
出典:公益財団法人 生命保険文化センター 特定の病気などに備える生命保険の加入率は?
がんの罹患率
出典:厚生労働省 令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告
がんに関する治療費平均額
出典:公益社団法人全日本病院協会 医療費(重症度別)【年間】2023年度年間集計
高額療養費制度について
出典:全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき
アメリカでの若年層(15〜39歳)におけるがんの罹患率上昇
出典:シカゴ大学医療センター「Why are more young people getting cancer? What to know as cases rise」
肥満や加工食品、運動不足などの生活習慣とがんリスクの増加の関連性
出典:ハーバード公衆衛生大学院「Lifestyle changes may be driving higher cancer rates in people under 50」

 FP相談予約
FP相談予約











