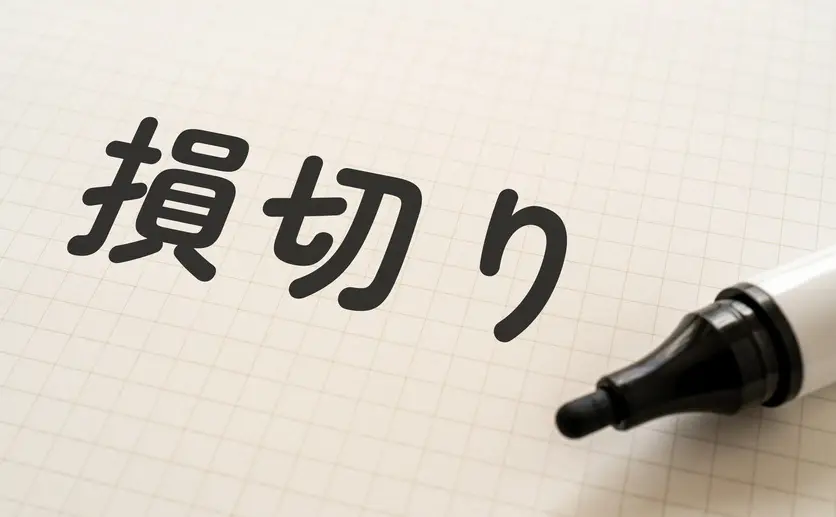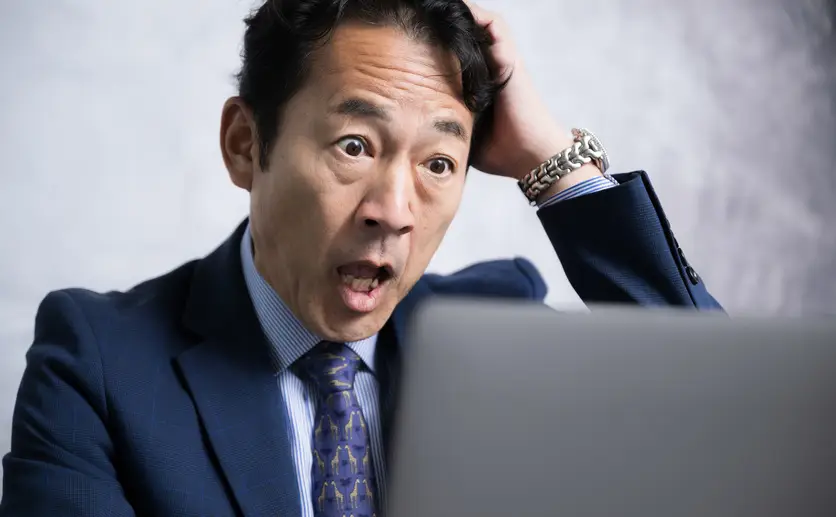新しいNISAのつみたて投資枠でよくある失敗とは?原因と対処法を解説します

NISAのつみたて投資枠は、少額から資産形成を始められるという点で「初心者向け」と言われることも少なくありません。しかし、初心者向けといっても100%安全な投資方法というわけではなく、やり方を間違えると失敗するケースもあります。
NISAのつみたて投資枠で運用する際は「長期投資」や「分散投資」を意識することが大切です。
本記事では、NISAで投資初心者が陥りやすい失敗例を確認しながら、リスクを抑える方法や、つみたて投資枠の活用方法まで詳しく解説します。
【ここをクリック】NISA初心者でも大丈夫!丁寧にお教えします|ソナミラでFP相談してみよう
新しいNISAのつみたて投資枠での失敗例

NISAでは、従来の制度よりも非課税投資枠の拡充や非課税期間の撤廃で、自由度高く運用できるようになりました。一方で、自分で銘柄選びや売買のタイミングを判断しなければならないため、初心者にとっては難しく感じられる場面もあります。
NISAにはデメリットしかないと考えている人は、次の記事で専門家の意見を見てみましょう。
▶【関連記事】NISAは本当にデメリットしかないのか?FPが解説するNISAの真実とは
毎月の積立額を多くしすぎてしまう
NISAのつみたて投資枠では年間120万円まで、月あたりに換算すると10万円まで投資できるようになっています。
貯蓄を習慣化するために、毎月の収入のうち一定割合を先に貯蓄に回す「先取り貯蓄」をすることは大切です。しかし、積立金額を多くしすぎると家計が苦しくなり、途中解約(投資信託の売却)や積立金額の変更を余儀なくされてしまいます。
NISAで保有している商品を途中売却するとき、購入時よりも基準価額が下がっていると、損失が発生する可能性があります。
もちろん、NISAでは一生涯投資できるので、一旦多めの資金で始め、家計に負担が生じていると感じたときに金額を減らすことも可能です。しかし、積み立てる金額を途中で増減させるとドル・コスト平均法の効果を十分に得られなくなります。
ドル・コスト平均法とは、価格の変動する金融商品を、一定金額で定期的に購入する方法のことです。価格が高いときには量を少なく、価格が低いときには量を多く購入できるため、結果的に平均購入単価が平準化されるというメリットがあります。
しかし、途中で金額を変更すると「安いときに多く買えない」「高いときに買い過ぎてしまう」といったことが起こり、ドル・コスト平均法によるリスク低減の効果を得られなくなる可能性があります。
新しいNISAで損失が出たときの対処方法を知りたい方は次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】新NISAで損失が出ている時の対処法3選!損切りは正解なの?
商品選びを誤った
NISAのつみたて投資枠では、金融庁が厳選した「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」が投資対象となっているため、多くの選択肢から個人で投資商品を選ぶ場合と比べて、失敗を避けられる可能性があります。
しかし、商品ごとにリスク、リターンには大きな違いがあるため、投資目的に合わない商品を選んでしまうと、良い結果が得られないこともあります。
たとえば、収益性の高さを求めているのにもかかわらず、一般的にローリスク・ローリターンとされる債券を多く含むバランスファンドに投資した場合、期待するリターンは得にくくなるでしょう。
また、投資信託の運用中には「信託報酬」と呼ばれる、投資信託を運用・管理するための運用コストがかかります。
つみたて投資枠の対象銘柄は、信託報酬が低めに設定されている傾向があるものの、効率的な運用を目指すのであればより信託報酬の低い商品を探すことをおすすめします。
すぐに売却してしまった
保有中の商品の基準価額が大きく値下がりした際に、焦って売却するのはよくある失敗例の一つです。
NISAで保有している商品はいつでも自由に売却できます。そのため、損失が膨らまないように売却する(損切り)ことや、一定の利益を得られた段階で売却する(利益確定)ことも可能です。
しかし、目先の値動きを気にしすぎて、損失が出るたびに売却をしていると、損失ばかりが積み重なり資金がふえにくくなってしまうこともあります。また、短期間で売ってしまうと、本来、長期運用していれば得られるはずだった利益を失うことにもつながりかねません。
基本的に、取引価格や基準価額は上下に変動を繰り返しているため、一時的に下落しても長期的に見れば元の水準に回復する可能性も十分あります。目先の値動きに惑わされず、長期的な投資を心がけることが大切です。
新しいNISAでコツコツ積み立てたのに暴落したら・・・そんな不安を抱える人は次の記事も参考にして下さい。
▶【関連記事】新NISAで積立てたのに!20年後に暴落したらどうなるの?
【ここをクリック】NISAで不安を抱えている人はアドバイスを受けてみませんか?ソナミラでFP相談してみよう
新しいNISAで運用の失敗を避ける方法

NISAのつみたて投資枠の投資対象は、元本保証のない投資信託やETFなどの金融商品で、必ず利益を得られるという保証はありません。しかし、長期的な目線で運用することや、分散投資を心がけることで、大きな損失を出すことを避けられる可能性があります。
長期的な視点を持つ
NISAでの失敗リスクを抑えるためには、日々の価格変動に振り回されず、長期的な視点で投資することが重要です。
株式や債券などの金融商品は、長期的に見れば投資収益率(リターン)のばらつきが小さくなる傾向にあります。金融庁のシミュレーションによると、1989年以降、毎月同じ金額を国内外の株式と債券に積み立て投資した場合、保有期間が5年で元本割れするケースが確認されましたが、保有期間が20年の場合は収益が安定し、元本割れしたケースはありませんでした。
さらに、長期間にわたって投資を続けると、複利効果も大きくなります。複利効果とは、投資から得た収益が再投資され、元本だけでなくその収益がさらに収益を生み出す効果です。
NISAは生涯非課税で保有できます。可能な限り運用期間を長く確保することは、リスクを抑える重要なポイントです。
分散投資を心がける
NISAでリスクをコントロールするためには、分散投資が大切です。分散投資は、複数の資産や地域に分けて投資することで、価格変動リスクを軽減する投資手法を指します。この方法では、一部の資産が値下がりしても、他の資産の値上がりで補うことが可能になるため、運用資産全体ではより安定したリターンが期待できます。
バランス型ファンドであれば、一つのファンドだけでも国内外の株式、債券、不動産(REIT)などに幅広く分散されているため、投資初心者でもリバランス不要でリスクを抑えた投資が可能です。
余剰資金で無理なく投資をする
NISAのつみたて投資枠で失敗しないためには、生活に影響が出ない範囲で、毎月の投資額を設定することが重要です。
投資金額をふやしすぎて家計の負担が大きくなってしまうと、生活資金を投資に回すことになってしまい、価格が下落した際に耐えられず、売却せざるを得なくなってしまうこともあります。余裕資金の範囲内で投資に取り組むことが大切であり、投資の基本原則の一つです。
運用目的や投資計画を決めておく
NISAで運用をスタートする前に、資産運用の目標金額などを明確に設定しておくことが大切です。「いつまでに」「何のために」お金を貯めるのかが明確になっていれば、投資すべきファンドや毎月の積立額を決定しやすくなります。また、目標があることで、予定外のタイミングで慌てて資金を引き出すことも少なくなるでしょう。
ざっくりとした目標でも問題ありませんが、NISAのつみたて投資枠は長期投資を前提としているため、「5年以内に資産を倍にしたい」といった短期的な目標の実現は難しい場合があります。
新しいNISAのつみたて投資枠を有効活用

NISAのつみたて投資枠を有効活用するためには、金融機関選びも重要です。金融機関や銘柄の選び方がわからない場合や、売買のタイミングなどを相談したい場合は、お金や資産運用のプロに相談してみましょう。
自分の投資したい商品のある金融機関を選ぶ
つみたて投資枠の取扱銘柄は、金融機関(証券会社や銀行など)によって異なります。NISA口座の開設は全ての金融機関を通して1人1つと決まっているので、自分の投資したい銘柄を扱っている金融機関を選びましょう。
もしまだ決まっていない場合は、取扱銘柄数の豊富な金融機関を選ぶと、あとで「投資したい銘柄がない」という事態を避けやすくなります。大手ネット証券は、取扱銘柄数が豊富な傾向にあります。
なお、つみたて投資枠の場合、どの金融機関を選んでも購入時の手数料は原則無料です。
不安なときや困ったときはプロに相談する
NISAのつみたて投資枠を活用するにあたって、金融機関や商品選び、売買のタイミングなどに迷った場合は資産運用の専門家に相談してみましょう。IFA(資産運用アドバイザー)等に相談すれば、専門知識を活かして、相談者のニーズや家計の状況に合わせて的確なアドバイスを受けられます。
ソナミラでは、資産運用や保険に詳しいコンシェルジュに無料で相談できます。店舗での相談だけではなく、オンラインでの相談にも対応しているため、空き時間で気軽に話を聞きたい場合にもぴったりです。
新しいNISAで失敗しない!Q&A

新しいNISA制度は、2024年から大きく制度が刷新され、非課税枠の拡大や期間の恒久化など、投資初心者にとっても始めやすい制度となりました。しかし、仕組みを正しく理解せずに始めてしまうと、思わぬ損をしてしまうことも。ここでは、NISAのよくある疑問や注意点をQ&A形式で解説し、成功するための(失敗しないための)ポイントを紹介します。
Q1. そもそも新しいNISAってどう変わったの?
2024年からの新しいNISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが併用可能になり、年間最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯で1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)までの非課税投資が可能になりました。運用益や配当金も非課税になるため、長期の資産形成に最適です。
新しいNISAで運用をすべきか悩んでいる人は、後悔しないかどうかを次の記事でチェックしてください。
▶【関連記事】新NISAこんな人はやめとけ!後悔するかもしれない3つのタイプ
Q2. つみたて投資枠と成長投資枠、どちらを優先すべき?
つみたて投資枠で行う積立投資は、価格変動リスクを抑えながら安定的に資産をふやす方法で、投資初心者にも向いています。一方、成長投資枠では個別株やETFなども自由に購入できる反面、損失リスクも伴うため、商品選びに注意が必要です。まずはつみたて投資枠で基礎を固めたうえで、余裕資金で成長投資枠を活用するのが安心です。
成長投資枠での運用やETFに興味がある方はこちらも参考にしてください。
▶【関連記事】新NISAで投資信託orETF?FPが教えるお得な選び方とは
Q3. iDeCoとNISAはどう違う?併用はできる?
iDeCoは「老後資金のための私的年金制度」で、所得控除による税制優遇が受けられますが、原則60歳まで引き出せません。一方、NISAはいつでも売却・出金可能です。目的やライフプランに応じて併用も可能ですが、目的別に分けて使い分けるのがポイントです。
Q4. 投資初心者がやりがちな失敗は?
投資初心者がNISAを始める際、最も陥りやすいのが「基本的な知識を理解しないまま始めてしまうこと」です。その結果、次のような3つの典型的な失敗が多く見られます。上述した部分と重複しますが、重要なポイントですので再度確認しておきましょう。
- 無理な金額で積立を行い、生活費を圧迫してしまう
「積立投資は続けることが大事」と聞いて、家計収支に見合わない金額を設定してしまう方が少なくありません。たとえば月10万円を積み立てれば年間で120万円の非課税枠を最大限活用できますが、それが家計を圧迫してしまっては本末転倒です。
生活費や急な出費に備える現金が不足すると、せっかくの投資信託を途中解約する事態になりかねません。このように、お金が必要だからと本来想定していないタイミングで解約すると、その時の相場環境が下落局面の場合、元本割れするリスクも高まります。積立額は「今の生活に無理のない金額」で設定することが大切です。 - 商品を利回りランキングだけで選ぶ
「利回りが高い=良い投資先」と思い込み、年利10%超の実績がある商品を理由なく選んでしまうケースも見受けられます。しかし、短期的に利回りが高いということは、それだけ価格変動が激しいハイリスク商品である可能性も高くなります。
投資信託にはそれぞれ異なる運用方針や資産構成があり、自分の投資目的に合った商品を選ばなければ思うような結果は得られません。たとえば「安定運用をしたい」のに、新興国株100%のファンドを選んでしまえば、想定以上のリスクを背負うことになります。商品の選定は、利回りだけでなく、信託報酬・資産の分散状況・過去の運用方針など総合的に比較する視点が求められます。 - 値下がりを恐れてすぐに売却してしまう
投資を始めてすぐ、購入した投資信託が数%下落しただけで「損した!」と感じ、焦って売却してしまうのもよくあるパターンです。これは長期投資というNISAの本来の目的から逸脱している行動であり、特に初心者が最も避けたい失敗です。
将来の価格変動は誰にも予測できませんし、市場全体が一時的に下がっているだけということもよくあります。しかし、感情に任せて売却してしまうと、本来得られるはずだった複利効果や将来的な回復の恩恵を逃してしまうことになります。特にNISAは非課税期間中に得られる利益が大きな魅力ですから、焦らずに「長く持ち続ける」ことが成功の秘訣です。
正しい知識を身につけ、感情に左右されずに中長期の視点で運用を継続することが何よりも大切と理解しましょう。
Q5. どこでNISA口座を開くべき?おすすめは?
金融機関によって取り扱い銘柄やサービスの詳細が異なります。国内の大手ネット証券では、手数料が安く、取扱銘柄も豊富です。また、投資コンテンツやランキング形式の情報も充実しており、初心者でも使いやすい設計になっています。
まずは自分が買いたい投資信託や株があるかどうかを確認しましょう。サイトでの検索機能や新着情報の更新もチェックポイントです。
Q6. 法人名義でNISAは使える?
いいえ、NISAは一人一口座、個人名義専用の制度です。法人では利用できません。法人での投資は、別途証券取引口座を開設する必要があります。なお、NISAで得た運用益には税金がかかりませんが、法人口座では通常課税対象になります。
Q7. 今後も制度変更はあるの?
2024年に新制度として始まったNISAですが、政府や金融庁の方針により今後も細かな変更や更新が行われる可能性はあります。制度変更される際には、あらかじめ金融庁のホームページで詳しい情報が提供されるため、最新情報を確認するよう心がけましょう。
Q8. 参考にするべき情報源は?
新しいNISAについて知識を深めるには、金融庁や証券会社のサイトだけでなく、信頼性の高い比較サイトやネットのQ&Aコンテンツも活用しましょう。監修者の明記された情報や、2025年以降の法改正にも対応した記事は特に有用です。
Q9. NISAを成功させるために最も重要なことは?
何よりも重要なのは、投資の目的を明確にすることと、自分に合った投資スタイルを選ぶことです。感情に振り回されず、知識と情報を武器に、計画的に投資を行うことがNISA成功への近道です。自分のライフプランに合った活用法を探ることが、最大の成果を得るポイントといえるでしょう。
失敗を避けるには計画的な運用が大切

NISAのつみたて投資枠は、売買のタイミングや銘柄選び、投資上限額などの面で、投資家の裁量が大きい制度です。うまく活用できれば、資産形成に大きく寄与しますが、短期的な価格変動に一喜一憂したり、手数料の高い商品に投資したりすると、思うような成果を得られないこともあります。
運用中のリスクをなるべく抑えるためには、中長期的な資産運用の目標を決めた上で、家計に無理のない金額で積み立てを始めることが大切です。その際は、投資する銘柄もなるべく分散させるとよいでしょう。
資産運用の目標の決め方や、銘柄の選び方に悩む場合は、お金のプロに相談することをおすすめします。
ソナミラでは、IFA登録であるコンシェルジュに無料で相談できます。オンライン相談と店舗での相談、どちらにも対応していますので、NISAをはじめとして、資産運用に関する悩みがある方は、無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
【ここをクリック】NISAの相談はコンシェルジュに!ソナミラでFP相談してみよう
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考
NISAについて
出典:金融庁「NISAを知る」
NISAの仕組み
出典:金融庁「NISA 早わかりガイドブック」
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号

 FP相談予約
FP相談予約