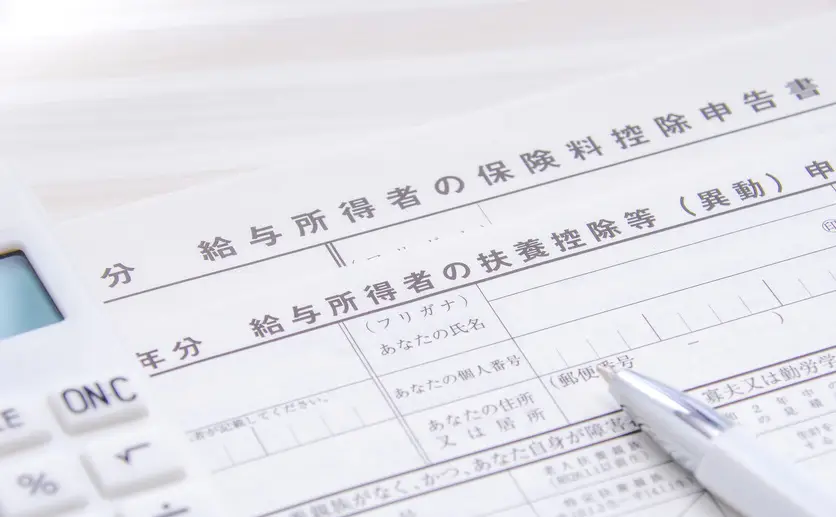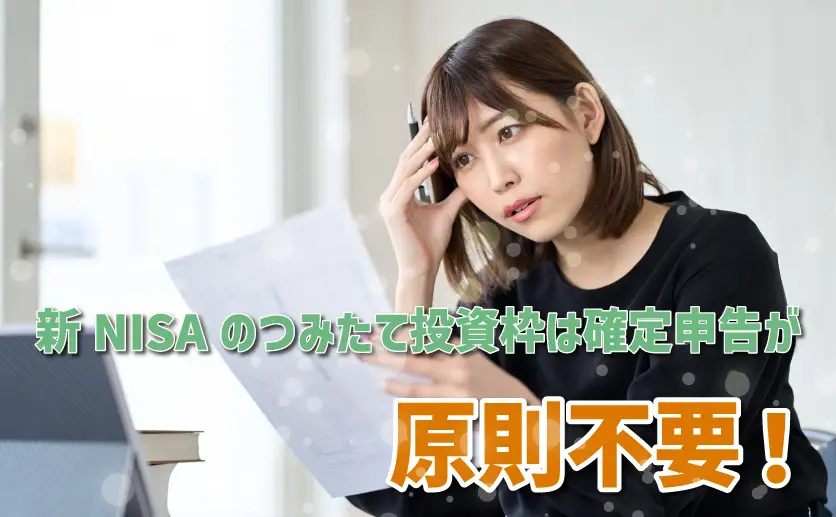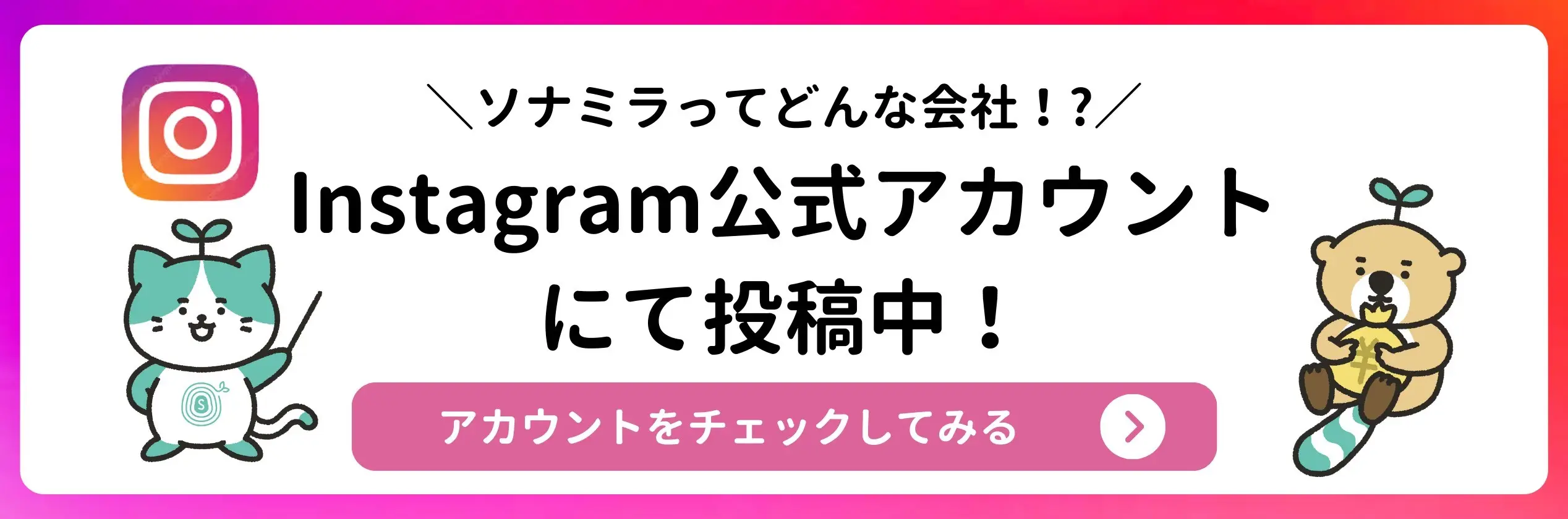年末調整の還付金はいつもらえるの?戻ってくる人と時期、計算方法を解説

会社員の人であれば一度は耳にしたことがある「年末調整」。しかし、どういう仕組みでお金が戻ってくるのか、詳しく理解している人は多くないのではないでしょうか。
年末調整の仕組みは初心者にはやや難しく感じるかもしれませんが、この記事では例を交えながらガイド形式で解説しています。
この記事を通して、年末調整や還付金に関する基本的な知識を身につけましょう。
【ここをクリック】年末調整について不安があるときはソナミラでFP相談してみよう
年末調整と還付金の関係を知ろう!

年末調整とは、1年間に源泉徴収された所得税と、 本来納めるべき正しい税額との差を計算し、精算する手続きです。その結果、税金を多く納めていた場合は、差額が「還付金」として戻ってくることがあります。
ここでは、年末調整の必要性や対象者、還付金の考え方について解説していきます。
年末調整しないと控除が受けられない
年末調整とは、実際に納めるべき所得税額と、すでに納付した税額のギャップ(差)を確認し、それを調整するために会社が行う手続きのこと。あくまで「ギャップの調整」が目的のため、お金を受け取る(還付)だけではなく追加で支払う(不足額徴収)こともあり得ます。
これらの税額のギャップはなぜ生まれてしまうのでしょうか。企業は従業員に給与や賞与を支払うときに、あらかじめ所得税分を徴収しています(源泉徴収)。あくまでも仮定の所得額をもとに算出した税額のため、年末になって実際の所得額から算出した税額とは異なることがほとんどなのです。
年末調整をしないと、各種控除が受けられず、税金を多く支払うことになるため注意しなければなりません。
年末調整の対象者と注意点を知ろう
年末調整はすべての会社員が対象というわけではなく、「その年の12月31日時点で在籍している従業員」に対して実施されるのが基本です。途中で入社した場合でも、その年内に給与の支払いがあり、条件を満たせば対象となります。ただし、転職したばかりで前職の源泉徴収票が間に合わない場合など、企業によって取り扱いが異なることがあるため注意が必要です。
また、年末調整の対象者には一部のパート・アルバイトも含まれますが、給与や勤務時間などの要件を満たさないと対象外になる場合もあります。具体的な該当条件については、会社の労務管理や人事部門が保有している情報に基づいて判断されるため、確認しておきましょう。
還付金は払い過ぎた税金の戻り分
先述した通り、還付金とは、税金を支払い過ぎた場合に、納税者に返還されるお金のことです。還付を受ける方法には、自ら税務署で手続きをする「確定申告」と会社が手続きをする「年末調整」の2種類があります。原則として会社員の場合、確定申告は必要ありません。
ただし、以下のようなケースに当てはまる場合は会社員でも確定申告が必要です。
- 2か所以上から給与をもらっている
- 副業の収入が20万円を超えている
- 年収が2,000万円以上である
- 住宅ローン控除※や医療費控除などを受ける
※初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で対応可能です
具体的な計算例
年末調整の計算方法をより理解するために、具体例を見てみましょう。この計算例はあくまで、還付金のイメージを持っていただくためのものであり、実際の計算とは異なることがありますので、詳細は税務署等にご確認ください。
【具体例1】年収500万円の会社員Aさんの場合
- 給与収入:500万円
- 給与所得控除後:334万円(給与所得控除166万円)
- 社会保険料控除:60万円
- 生命保険料控除:4万円
- 基礎控除:48万円
- 課税所得:334万円 - 60万円 - 4万円 - 48万円 = 222万円
- 所得税額(税率10%):222万円 × 10% - 2.97万円(税額控除*) = 19.23万円
*所得控除は「課税対象を減らす」しくみ、税額控除は「税金そのものを直接差し引く」しくみです。控除の種類によって、効果が異なります
このAさんが毎月の給与から源泉徴収で納めた所得税が合計22万円だった場合、年末調整で還付される金額は: 22万円 - 19.23万円 = 2.77万円となります。
【具体例2】マイホームを購入した会社員Bさんの場合
- 給与収入:600万円
- 住宅ローン控除額(住宅ローン残高の0.7%):17.5万円
- 通常の所得税額計算後:25万円
- 年末調整後の所得税額:25万円 - 17.5万円 = 7.5万円
元々源泉徴収されていた所得税が25万円なので、17.5万円が還付されることになります。
このように、控除の種類や金額によって、還付される金額は大きく変わります。自分の状況に当てはめて、概算でも還付金を事前に把握しておくと安心です。
年末調整と確定申告の違いとは?
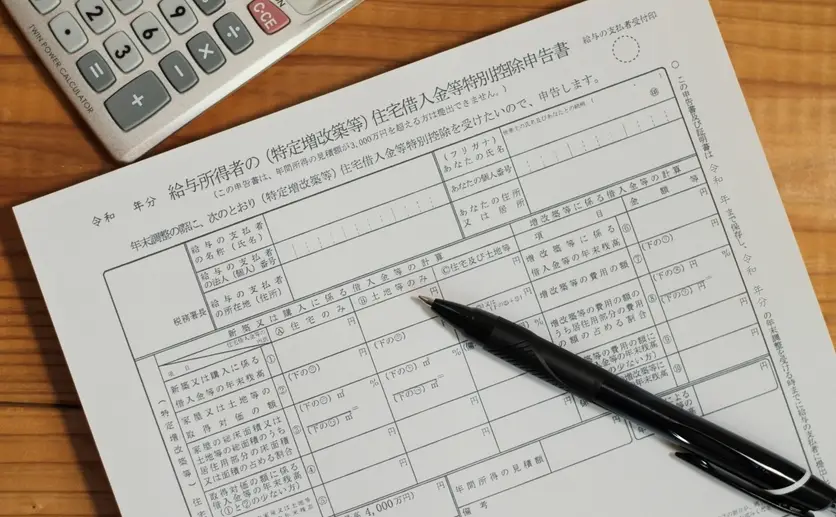
年末調整も確定申告もよく聞く言葉ですが、どのような違いがあるのでしょうか。ここでは、その違いを分かりやすく解説するとともに、2024年度から導入された「定額減税」についても紹介します。
年末調整も確定申告も税金の精算が目的
年末調整と確定申告は、どちらも税金の精算を目的としていますが、対象者や実施方法に違いがあります。会社員であれば、通常は勤務先が年末調整を実施するため、自ら申告する必要はありません。ただし、医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除の初年度などは、年末調整では対応できないため、自分で確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告では復興特別所得税の扱いにも注意が必要です。これは東日本大震災に伴い導入された税で、所得税とともに計算されます。年末調整でも同様に扱われますが、申告内容によっては差額が生じる可能性があります。
定額減税の導入と年末調整への影響
2024年度から新たに導入された「定額減税」は、一定の所得者に対して税負担を軽減する制度です。これは給与所得者が受け取る基礎控除の一部強化とも言える内容で、年末調整にも関係します。
会社は対象となる従業員に対して、年末調整時に自動で控除を反映することが求められますが、導入直後の制度のため、処理を誤ると控除漏れが発生するリスクもあります。社内の従業員数や導入しているソフトウェアの機能によっては、業務の負担が急増することも懸念されているのです。
最新の対応策としては、クラウド型労務管理ツールとの連携を活用し、控除対象の自動判別や一覧表示でのチェックを行う企業も増えています。年末調整の流れに組み込むことで、社会保険や税の関連情報を一元化しやすくなり、効率的な処理が可能になります。
この定額減税によって、年収500万円で扶養家族1人の人は、最大4万円程度が年末調整で差し引かれるケースが想定されます(2024年度時点)。
還付金を受け取るタイミング

年末調整の還付金は多くの場合12〜1月に受け取れます。ただし、還付のタイミングや方法は会社によって異なるため注意しましょう。
年末調整による還付金は、給与と一緒に支給されるケースが一般的です。この場合、振込金額の内訳として、給与明細に還付金の金額が明記されているので、忘れずに確認しましょう。
なお、還付の時期は、企業の人事や経理部門が使用する給与計算システムや勤怠管理の仕組みによって異なる場合があります。たとえば、給与の締め日が早い会社では、年末調整の反映が翌月にずれることもあります。
また、 12月末の時点で在籍していない社員には還付金が支給されないケースもあるため、会社ごとの法人規定や適用要件も事前に確認しておくと安心です。
12月分の給料と合わせて受け取る
一般的なのは、12月の給与支給日に、給与と一緒に還付金が振り込まれるパターンです。12月上旬に賞与と合わせて支払われるパターンもよくあります。
翌年1月分の給料と合わせて受け取る
繁忙期を避けたい、給与の締め日が早いなどの理由で、12月中に年末調整が間に合わないことがあります。その場合、翌年1月分の給料と合わせて還付金が支払われるケースもあります。
12月〜翌年1月の間に現金で受け取る
12月〜翌年1月の間に、年末調整が終わり次第、給与とは別に手渡しや振り込みなどの方法で還付金が支払われるケースもあります。
12月31日と1月1日が重要な基準日になる理由

年末調整の対象者は「12月31日時点で在籍している社員」と法律で定められています。逆に、1月1日に入社した場合は、当年の年末調整の対象外となり、翌年度からの対象になります。
この「年度の区切り」があるため、12月末での退職・転職など、勤務状況に変更があった人は特に注意が必要です。源泉所得税や住民税との関係もあるため、必要であれば税理士や専門機関に相談しましょう。
【ここをクリック】自分にはどんな還付金があるのかな?悩んだ人はソナミラでFP相談してみよう
こんな人は還付金を受け取れる可能性大
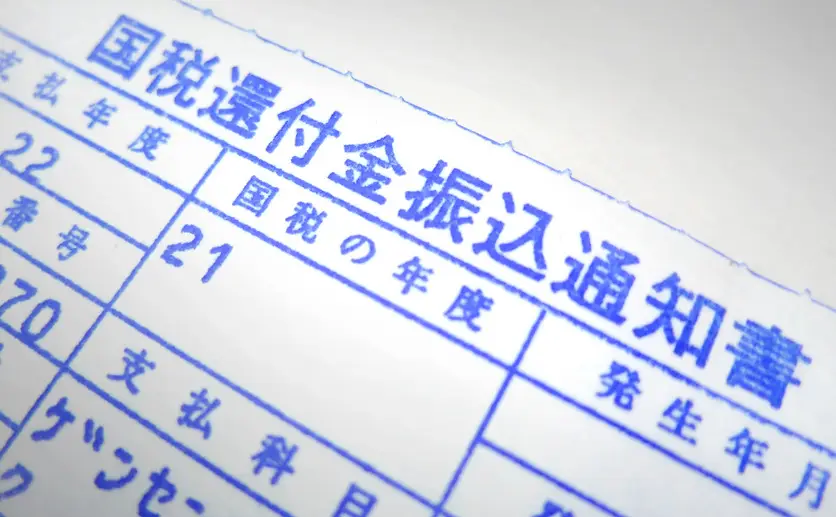
年末調整によって還付金が受け取れる人は、実は多く存在します。
特に「年収はそれほど高くないけれど保険に入っている」「住宅ローンを組んだばかり」といったように、一定の支出がある人ほど、所得控除を受けやすくなります。
たとえば、生命保険や医療保険、住宅ローン、扶養家族の増加などは、いずれも控除の対象になり、結果的に税金が戻ってくる(還付金)可能性が高くなるのです。
年末調整の時期に「会社から言われたから書類を提出するだけ」で済ませてしまう方も少なくありませんが、自分がどの控除を受けられるかを一度整理しておくことが大切です。制度を正しく理解すれば、思っていた以上にお金が戻ってくることもあります。申告のチャンスを逃さないようにしましょう。
特に最近では、副業や扶養の変化などライフスタイルが多様化しているため、早めの確認がいっそう重要です。
年末調整で計算した「1年間に納めるべき所得税額」よりも「実際に納めた所得税額」が多い場合には還付金が受け取れます。基礎控除や給与所得控除以外にも所得控除を受けられる場合、還付金を受け取れる可能性は高いです。
所得控除とは、課税所得を算出する際に、給与所得から一定額を差し引くことを指します。所得控除により課税所得が減ると、支払うべき税額は減るため、還付金が受け取れる仕組みです。たとえば、所得税率が10%のとき、50万円の所得控除を受けられる場合には、50万円×10%=5万円分の還付が受けられます。
最近では副業やダブルワークをしている人も増えており、2か所以上から給与を受け取っている場合は、年末調整だけで正確な納税ができないことがあります。このようなケースでは確定申告を行い、税額の差額精算が必要です。
また、副業による収入は、本業の給与とは異なり、源泉徴収がされていないこともあるため、自分で正確に申告しなければなりません。申告漏れや誤りがあると、過去の年度にさかのぼって追徴課税されることもあります。
個人で生命保険や損害保険などに加入した人
生命保険や損害保険に加入した人は、払い込んだ保険料に応じて生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除を受けられるため、還付金を受け取れます。
控除対象となるのは、生命保険や医療保険、個人年金保険などが挙げられます。また、保険に関連する控除としては、地震保険料控除もあります。ただし、地震保険は控除対象となりますが、一般的に地震保険とセットで加入することが多い火災保険については基本的に控除の対象外ですので区別して理解しておきましょう。
生命保険料控除は最大で12万円、地震保険料控除は最大で5万円となっています。
家族の社会保険料を納付した人
家族の年金保険料や健康保険料を支払った人は、社会保険料控除を受けられるため、還付金を受け取れます。支払った社会保険料の全額が所得から控除されます。
住宅ローンを組んでいる人
住宅ローンの支払いをしている人は住宅ローン控除の対象となるため、還付金を受け取れます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、ローン残高の0.7%を最大13年間(※令和4年度税制改正以降)、所得税から控除する制度のことです。
年末調整で手続きできるのは2年目から。1年目に還付を受けるためには、確定申告が必要です。
iDeCoに加入している人
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人は小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、還付金を受け取れます。掛け金全額が所得控除の対象となります。
扶養する家族が増えた人
扶養する家族が増えた場合は、扶養控除や配偶者控除などの所得控除の対象となるため、還付金が受け取れます。年間の合計所得金額が48万円以下、納税者と同一生計などの条件を満たす親族がいる場合に扶養控除の対象となります。
具体的な控除額は以下の通りです。
- 19歳以上23歳未満の親族(特定扶養親族):63万円
- 70歳以上の親族(老人扶養親族):48万円(同居の場合は58万円)
- それ以外の親族:38万円
給与収入が103万円以下の配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者本人の所得に応じて13〜38万円(70歳以上の場合は16〜48万円)の所得控除を受けられます。
また、配偶者の給与収入が103万円を超えても一定金額までならば、「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
配偶者がいなくなった人
離婚や死別などを経験し、一定の条件を満たした場合は、寡婦控除の対象となり、還付金が受け取れます。寡婦控除は所得控除の一つで、控除額は27万円です。
自分や家族が障害を負っている人
自分や同一生計の家族が障害を負っている人は、障害者控除の対象となり、還付金を受け取れます。控除額は27万円です。重度の障害がある場合は40万円(同居の場合は75万円)となります。
還付金をもれなく受け取るためのコツ

年末調整の手続きの流れを把握し、提出書類の準備は早めに完了させるのが理想的です。提出期限や通知の有無、社内システムでの設定方法は、事前に人事担当からの連絡を確認しましょう。書類の送信ミスや記載ミスがあると、正しい処理がされず、還付金を受け取れない可能性もあります。
面倒な手続きだと感じるかもしれませんが、年末調整により数万円単位でお金が戻ってくる可能性もあるため、忘れずに申請しておきたいものです。
ここでは、還付金をもれなく受け取るために押さえておきたいポイントをご紹介します。
年末調整の手続きフローと必要な資料

年末調整をスムーズに行うには、手続きの流れと必要な書類を理解しておくことが大切です。
まず、10月〜11月頃に、勤務先から配布される各種申告書に記入する作業からスタートします。このときに必要となるのが、「保険料控除証明書」や「住宅ローン控除証明書」など、1年間の支払い実績を証明する資料です。
次に、記入済みの書類と添付資料を提出することで、会社の労務・会計部門が年末調整を行い、還付または追加徴収額を精算します。これにより、12月の給与で調整が行われ、もらえるまたは支払う金額が確定します。
年末調整の申告書は電子申請も可能で、クラウド型の会計ソフトなどを活用することでスムーズに手続きが進む場合もあります。
ここでは、手続きフローと必要な書類を細かく解説していきます。
年末調整の手続きフローを確認する
上述した年末調整の手続きは次のようなスケジュールで進行します。この流れを把握しておくことで、書類の提出忘れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。特に控除証明書は10月頃から届き始めるため、紛失しないよう保管する習慣をつけましょう。
10月中旬~下旬
- 保険会社や金融機関から控除証明書が届く
- 会社から年末調整の案内が配布される
11月上旬~中旬
- 年末調整申告書類の記入・提出
- 必要書類の準備と添付
11月下旬~12月上旬
- 会社による年末調整の計算作業
- 還付金や追加徴収額の確定
12月中旬~下旬
- 給与での還付金支給または追加徴収
- 源泉徴収票の作成
翌年1月下旬
- 源泉徴収票の交付
- 修正があれば会社に連絡(遅くとも1月末まで)
控除証明書を保管しておく
控除証明書がないと、年末調整で控除が受けられなくなるため大切に保管しておきましょう。
控除証明書とは、生命保険料やiDeCoの掛け金、住宅ローンなどを支払ったことを証明する書類のこと。なくしてしまった場合、再発行できるケースもあるため、各機関に問い合わせてみましょう。
申告書に正しく記載する
申告書への記入間違いや記入漏れがないよう注意しましょう。
年末調整で提出が必要な書類は以下の3つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
自分が適用を受ける控除に対応した書類を記入しましょう。わからなければ企業の担当者に確認してみるのも一つの手です。
還付金の額に間違いがないか確認する
還付金が振り込まれたら、金額に間違いがないか確認しておきましょう。勤務先が振込額を間違えてしまう可能性もゼロではありません。
万が一誤りがあった場合、会社に申告して修正できるのは源泉徴収票の発行前や、1月末日までです。その期間を過ぎると自分で確定申告をしなければならないため、注意しましょう。
年末調整による還付金は、給与振込口座と同じ金融機関口座に振り込まれるのが一般的です。ただし、退職後に口座を変更した場合や、振込先が指定されていないと、受取が遅れることがあります。
また、e-Taxやクラウド会計ソフトを使って申告する場合は、マイナンバーと口座情報の紐付けが求められることもあり、最新の登録情報に更新されているか確認が必要です。
申告時に紙の申告書を使用する場合も、記入欄に金融機関名・支店・口座番号を正しく記載しましょう。間違いがあった場合は、税務署からの修正依頼の通知や支払遅延が発生するリスクもあるため注意が必要です。
よくある質問と誤解しやすいポイント

年末調整に関してよくある質問をいくつかご紹介します。
Q1:還付金はいくらぐらい戻るのですか?
A:概算ですが、年収や家族構成により数千円〜数万円が一般的です。控除の内容によっては、多かった差額分が返金されることもあります。
Q2:年末調整とふるさと納税の関係はどのようなものですか?
A:ふるさと納税による税控除を受けるには、基本的に確定申告が必要です。ただし、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をしなくても控除を受けられます。この特例を利用しない場合は、年末調整だけでは控除が適用されないのでご注意ください。ワンストップ特例制度は、寄付先が5自治体以内の場合に利用できる簡便な手続き方法です。
Q3:間違えて提出してしまった場合はどうなりますか?
A:会社の年末調整処理が完了した後に誤りが発覚した場合、結果の修正が間に合えば対応してもらえるケースもあります。ただし、源泉徴収票が発行された後や翌年に入ってから判明した場合は、自分で還付申告を行う必要があります。
Q4:年末調整書類の提出が遅れるとどうなりますか?
A:会社の締切までに申告書が提出できないと、その年の年末調整に反映されず、自分で確定申告しなければなりません。
Q5:申告内容のどこに気をつけるべきですか?
A:まず、源泉徴収票の内容と申告書の記載に矛盾がないよう確認することが重要です。また、支払済の生命保険料や医療費の金額は、証明書と一致しているかチェックしましょう。必要な書類の添付漏れや、金額の入力ミスも毎年多く発生しています。
Q6:年末調整でよくあるミスにはどんなものがありますか?
A:代表的なものには、「保険料控除証明書の紛失」「住宅ローン控除の初年度に確定申告が必要なことを知らなかった」「氏名・扶養家族の記入ミス」などがあり得ます。これらのミスがあると、会社がいくら業務として正しく処理を行っていても、控除が適用されません。
Q7:ミスを防ぐためのコツはありますか?
A:会社から配布された案内やチェックリストを一覧として活用するのがおすすめです。記入漏れがないよう、申告内容をコピーして保管する習慣をつけると、翌年以降にも役立ちます。わからない点があれば、社内の担当者やサポート窓口に早めに確認しましょう。
Q8:効率的に申告を進めるにはどうすればいいですか?
A:最近では、クラウド型の年末調整作成サービスを導入している企業も増えています。自動計算やチェック機能があるため、入力ミスを大幅に削減でき、効率化にもつながります。利用している人は、早めにログインし、案内に沿って入力を進めておくと安心です。
年末調整の還付金を正しく受け取ろう
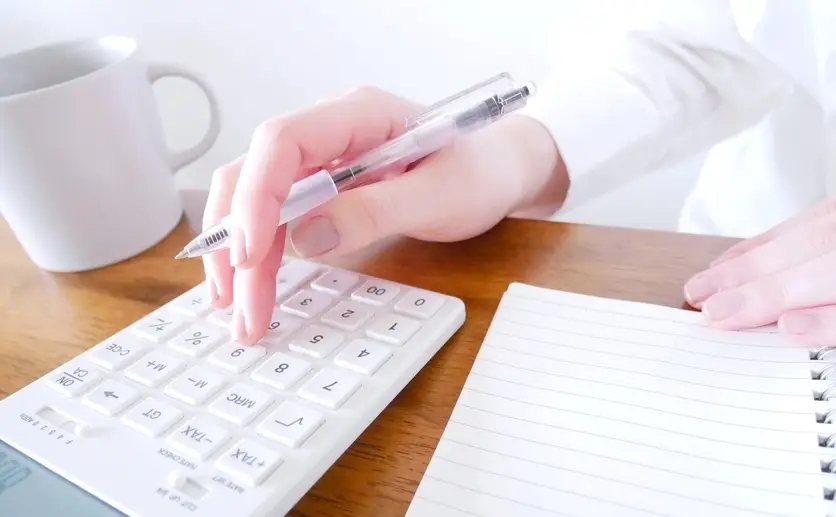
会社員の立場であっても、年末調整の仕組みを知っておくことは大切です。最近では、税理士や社労士が登壇する無料セミナーや、Web上で視聴できる研修動画なども増えており、「いつ、何をやればいいか」を理解するのに役立ちます。
特に、自営業や副業をしている人に加え、住宅ローンを返済中の人や保険に加入している人、介護にかかるお金が気になる人などにもおすすめです。そうした人にとって、制度のしくみや得られるメリットを知るよい機会になります。
また、税金の知識に自信がない人や、専門用語がわかりにくいと感じる人にも、資料がついているセミナーなら安心して学ぶことができます。
年末調整の還付金が受け取れるタイミングは、勤め先の企業によってさまざまです。また、受け取れる金額は、家族構成や所得控除の種類によっても変わります。自分がどのくらいの還付金を受け取れるのか、年末調整を迎える前に計算してみるとよいかもしれません。
また、そもそも手続きに誤りがあると、本来受け取れるお金が受け取れなくなる可能性があります。
今回の内容を参考にしながら、正確に手続きを進めていきましょう。
【ここをクリック】お金のことならなんでも相談できます!ソナミラでFP相談してみよう
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考
扶養控除の控除額について
出典:国税庁No.1180 扶養控除
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号