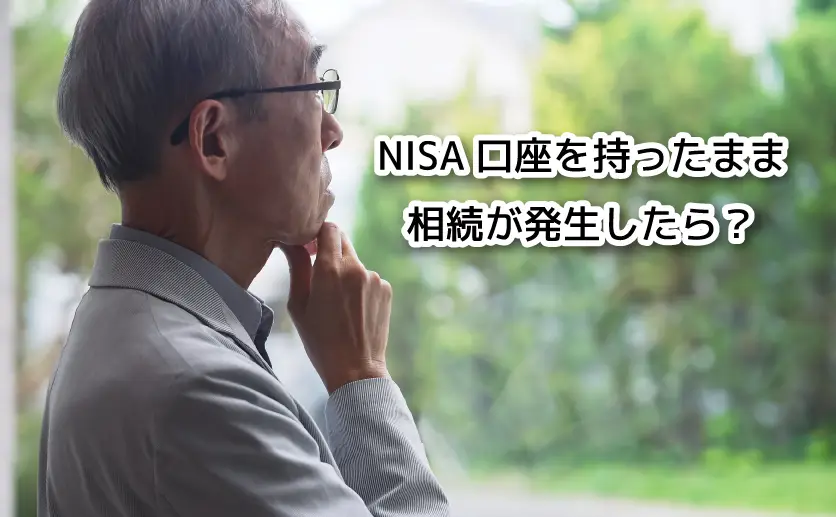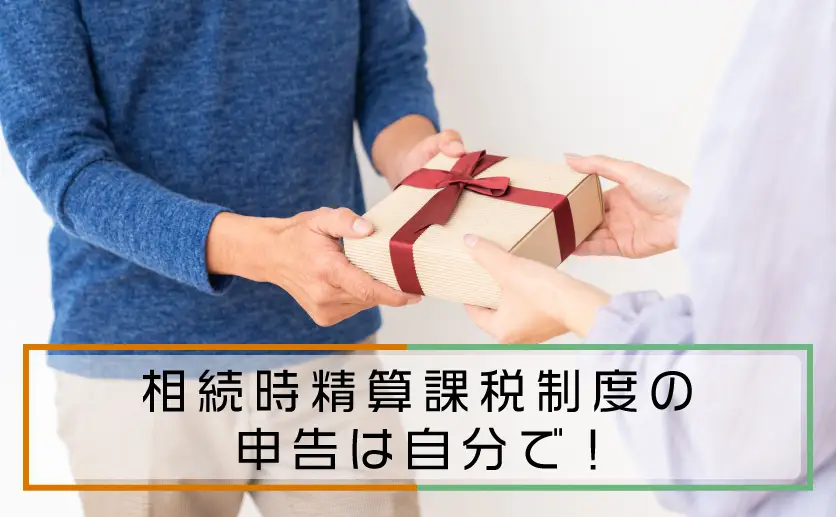相続税の基礎控除とは?配偶者控除を適用する方法と相談前の注意点も解説

節目の季節には、家族で集まる機会が多く、家族が集まったことで、親世代の相続について考えた人も少なくないのではないでしょうか。相続には相続税がつきものですが、相続税の基礎控除や対象の財産について確認しておけば、必要な対策をとることができます。この記事では、難しいと思われがちな相続税について、詳しく解説していきます。
※相続税における「配偶者控除」は正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。本文では「配偶者の税額軽減」という呼び方で解説していきます。
【ここをクリック】相続に関する基本を学びたい方はソナミラのFP相談へ
相続税の基礎控除に関する基礎知識
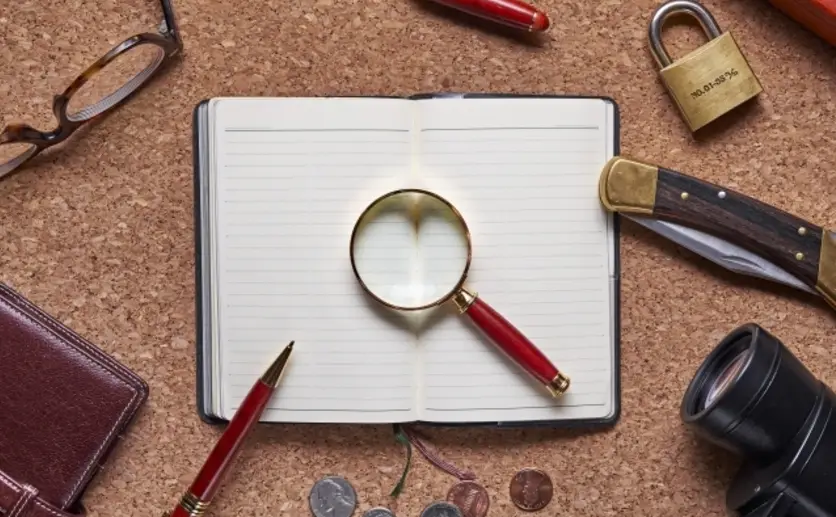
相続税の基礎控除とは、正味の遺産総額から差し引ける控除のことです。正味の遺産総額は、被相続人のプラスの財産から借入などのマイナスの財産を引いて計算します。この方法で計算した正味の遺産総額から、さらに基礎控除が引かれるのですが、基礎控除にはどのような意味があり、どうやって計算するのでしょうか。
基礎控除の意味
相続税は富の再分配を目的にしており、財産が多い人ほど税金も多く納める仕組みです。一方で、残された相続人の生活を守るために、一定水準までは相続税がかからないように基礎控除が定められています。遺産を相続した人は、基礎控除を超えた部分の財産にかかる相続税を納付しなければなりません。
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除は以下の計算式をもとに算出します。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除は法定相続人の数に比例して増加するため、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額も大きくなります。
たとえば、法定相続人が4人いる場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円と計算できます。正味の遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
なお、被相続人に養子がいる場合は、実子の有無によって法定相続人に含められる養子の数が異なります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人に含めることができます。
法定相続人の数え方と順位、範囲とは?

基礎控除を計算するうえで、法定相続人の数がポイントであることがわかりました。法定相続人はどのように数えたらいいのでしょうか。法定相続人の範囲や、法定相続人が亡くなった場合について、確認していきます。
法定相続人の範囲
法定相続人の対象者と順位は民法で定められており、被相続人の家族構成と被相続人の関係性によって、誰が相続人であるかが決まります。
被相続人の配偶者は常に相続人であり、配偶者以外は、以下の順序で配偶者と共に相続人として数えられます。順位が高い相続人がいる場合は、低い順位の人は相続人として数えられません(順位の高い人が相続放棄をした場合を除く)。
第1順位
被相続人の子ども
第2順位
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位
被相続人の兄弟姉妹
例として、家族構成が夫婦と子ども3人の場合を考えてみましょう。夫が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者である妻と子ども3人です。仮に夫の両親が健在であっても、相続の優先順位は子どものほうが上なので、相続人には含まれません。
なお、内縁関係の人は相続人には含まれませんので、注意が必要です。
家族構成に応じた遺産の分割と加算項目の整理
たとえば、被相続人が亡くなり、遺産が配偶者と子供に分割される場合、「遺贈」として特定の子供にのみ資産を残すような内容が遺言に記載されていることもあります。この場合、他の相続人は異議申し立てができる「遺留分」に関連して調整が必要です。
また、遺産の中に業務資産(自営業の事務所など)や債務(住宅ローン、事業資金)が含まれる場合は、相続人の負担割合にも配慮が求められます。さらに、納税資金の確保として、生命保険を活用したり、相続発生後すぐに預金を引き出すことで「葬式費用」などに充てる準備も重要です。
法定相続人が亡くなっていたらどうなる?
法定相続人が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。亡くなった相続人が被相続人とどういう関係だったかによって、状況が変わります。
被相続人の子どもが亡くなっている場合
被相続人の子どもが亡くなっている場合は、孫がいれば孫が法定相続人として認められます。これを代襲相続といい、本来相続人だった人が亡くなっていて相続できない場合に、その人の子どもが相続する制度です。
子どもが亡くなっていたら孫へ、孫も亡くなっていたらひ孫へ、というように、相続が発生した段階で次の世代がいれば、相続する権利を引き継いでいきます。なお、相続放棄をした人は、はじめから法定相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。
被相続人の配偶者が亡くなっている場合
被相続人の配偶者が亡くなっている場合は、子どもだけが法定相続人です。先ほどのケースであれば、被相続人の子ども3人ですべての財産を相続します。
相続税の計算に含まれる財産とは?

相続税はどの財産にかかるのでしょうか。被相続人が所有していた財産の中には、 相続税の計算に含まれる財産と、含まれない財産があります。
相続税と贈与税の違いと対応策
相続と関連する税金として、よく比較されるのが「贈与税」です。贈与税は、生前に財産を移転する場合に課される税金であり、相続税とは課税タイミングや計算方法が異なります。相続税は「亡くなったこと」によって発生しますが、贈与税は「生きている間の贈与」に応じて納税義務が生じる仕組みです。
この2つの税制の違いを理解することで、生前からの効果的な税対策が可能になります。なかでも多くの人が活用しているのが「暦年贈与」です。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額のうち、基礎控除額である110万円までは贈与税がかからないという制度です。この制度を利用すれば、年間110万円までの贈与を毎年繰り返すことで、将来的な相続財産を減らすことができ、結果として相続税の適正化につながります。
ただし、贈与があまりにも不自然だったり、形式的で実態のないものとみなされると、税務署から否認される可能性もあるため注意が必要です。たとえば、毎年同じ金額を同じ時期に振り込んでいる場合や、贈与された側が贈与の事実を把握していないようなケースでは、形式的な操作とみなされることがあります。贈与契約書を作成し、受贈者が自ら管理する銀行口座に贈与金を入金するなど、形式と実態の両面から「贈与が成立していること」を証明できるようにしておきましょう。
また、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、多額の贈与を一度に行うと逆に税負担が重くなるリスクもあります。「いくら贈与するか」「何年かけて行うか」は、財産全体の割合や相続人の人数、年齢などをふまえて計画することが重要です。
これらの制度を有効に使いこなすためには、税理士などの専門家と相談しながら「いつ、どのように贈与するのが最適か」を見極めることが望まれます。場合によっては、相続時精算課税制度の活用も含めた検討が必要になるため、早めの対応をおすすめします。
相続税がかかる財産
原則、亡くなった人の財産を相続によって手に入れた場合は、取得した財産に対して相続税がかかります。対象の財産は、現金、預貯金、株式や債券などの有価証券、土地や家屋などの不動産、自動車、宝石、著作権、特許権など、経済的価値のあるすべてのものです。
また、上記の財産に加えて、相続税法のルールにより、みなし相続財産として相続税の対象となるものがあります。たとえば、死亡退職金、被相続人が保険料を負担した生命保険の死亡保険金、被相続人から過去3年以内に贈与を受けた財産などです。
なお、相続財産の多くを占める不動産は、相続税評価額を算出したうえでそのほかの財産と合算しなければなりません。そのうえで、前述した基礎控除額を引きます。土地は原則、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価し、評価方法は地域によって路線価方式か倍率方式で計算します。家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
相続財産の評価額と税務調査の対象になりやすいケース
相続税の納税額は、遺産の評価額によって決まります。たとえば、不動産の評価には「路線価方式」や「倍率方式」などが用いられ、地域によって差が出るのが特徴です。また、都市部、特に東京都内のような地価が高いエリアでは、評価額が相対的に高くなる傾向があるため注意が必要です。
さらに、評価額を故意に安く見積もって申告した場合や、特定の財産が申告漏れとなっていると、税務署による調査の対象となる可能性があります。実際、預金口座の動きや不動産登記の履歴などから、税務署は詳細な調査を行います。税務調査は、亡くなってから2~3年後に行われることも多く、対応が後手になると延滞税や加算税の対象になることも。
そのため、評価資料は必ず保存し、見込額に不安がある場合は専門家と共に検討・申請しておくことが重要です。
相続税がかからない財産
財産の性質上、課税することがふさわしくないものに相続税はかかりません。
具体的には、墓地や墓石、仏壇など日常礼拝をしているものや、相続税の申告期限までに国または地方公共団体へ寄付したものなどがあげられます。
【ここをクリック】相続税がかかるのかな?と疑問に思ったらソナミラのFP相談へ
生命保険に相続税はかかるのか?

生命保険はみなし相続財産として相続税の計算に入りますが、前述した基礎控除とは別に相続税の非課税枠があります。そのため、非課税枠を超えた部分に対して相続税がかかります。
生命保険の非課税枠とは
生命保険金は、残された相続人が安定した生活を送るために重要な役割を果たします。そのため、一定の範囲内までは相続税がかからないよう、非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算式は、以下の通りです。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が4人いる場合の非課税枠は、500万円×4人=2,000万円です。相続放棄した人がいる場合や、養子がいる場合の法定相続人を数える方法は、基礎控除の計算と同様です。
相続放棄をした人も法定相続人の数に入り、実子がいる場合の養子は1人まで、実子がいない場合の養子は2人まで法定相続人としてカウントできます。
なおこの非課税枠は、各相続人が受け取る保険金ごとに適用される限度額ではなく、相続人全体で受け取る保険金の合計額に対して適用される限度額であることに注意が必要です。もし、法定相続人が4人いて、受け取る死亡保険金の合計額が3,000万円の場合は、3,000万円から2,000万円を引いた1,000万円に対して相続税がかかります。
配偶者控除を適用する方法は?

相続税の制度として一般に「配偶者控除」と呼ばれるものは、税法上は正式に「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。以下では、正確を期すため「配偶者の税額軽減」という呼び方を用いて解説します。
相続税の計算において、配偶者が受け取る財産に対して「配偶者の税額軽減」の特例を利用することで、納税額を大きく抑えることが可能です。これは、配偶者が取得した遺産が法定相続分か1億6,000万円以下であれば、原則として相続税が課されないという非常に大きな税額低減効果を持つ制度です。
この特例を適用するには、まず遺産分割を行い、配偶者が取得する財産を明確にすることが前提です。遺言書があればその内容に基づいて、無ければ法定相続分を考慮して分割します。なお、遺産の一部に未分割のまま残っている場合、特例が適用できない可能性があるため注意が必要です。
特例を受けるには、申告書類の提出が必須です。税務署へ相続税申告書とともに、戸籍謄本の写し、遺産分割協議書、遺言書の写し、資産評価に関する資料など、複数の添付書類を揃えて提出しなければなりません。書類の不備や提出漏れがあると、税務署から更正の請求を受けることや、税務調査に発展するリスクもあるため、提出時点でのチェックは徹底しましょう。
また、小規模宅地等の特例(居住用宅地は330平方メートルまで80%減額、事業用宅地は400平方メートルまで80%減額)や、障害者控除(85歳までの年数×10万円)、未成年者控除(18歳までの年数×10万円)など、他の制度と組み合わせて利用することで、税額低減効果を最大限に高めることも可能です。これらを採用するかどうかは、遺産構成や家族の事情、住所地(たとえば東京都か地方か)によっても変わるため、専門家と相談のうえで判断するのが望ましいでしょう。
専門の税理士法人や相続専門の事務所に依頼することで、書類作成から納税額の試算、対策方法まで一貫したサポートを受けることができます。費用はかかりますが、税額の減額幅を考えれば非常に合理的な選択肢です。
▶【関連記事】相続税は夫婦間でもかかる?1.6億円まで無税となる配偶者控除とは
税額控除や延長申請など知っておきたい制度
相続税の申告や納税では、状況に応じた各種控除制度や猶予制度を活用することが可能です。
たとえば、「税額控除」の一つとして、未成年者控除や障害者控除があります。これらは、該当する相続人が相続した場合に、相続税額の一部が控除される仕組みで、要件を満たすことで納税額を大幅に減らすことができます。
また、資金繰りが厳しい場合には、納税の延長や分割納付(延納・物納)も可能です。相続税の納税期間は原則として10か月以内と定められていますが、事前に申請を行えば、一定の債務や経済事情を考慮して納税猶予が認められることがあります。
なお、延長申請には税務署への手続きが必要であり、不要なトラブルを防ぐためにも、必ず提出期限前に対応することが求められます。
配偶者控除について相談するときの注意点
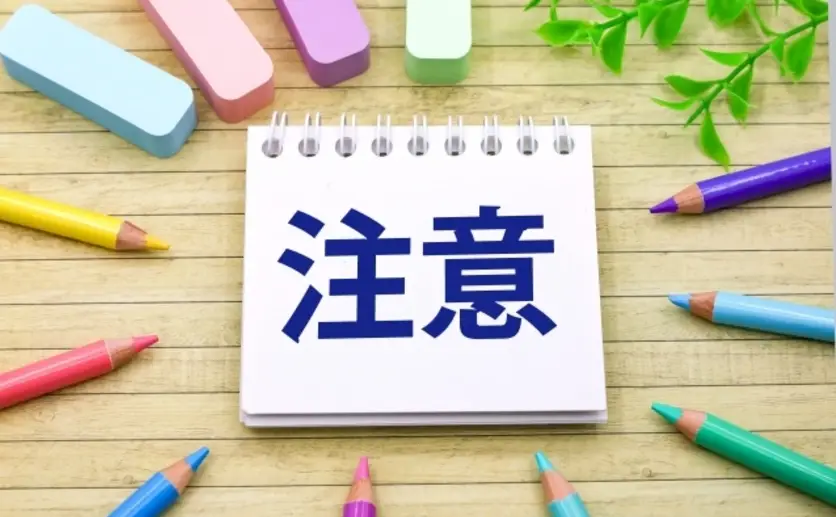
配偶者の税額軽減について税理士に相談を行う際には、いくつかの注意点があります。
まず、この 「配偶者の税額軽減」は所得税における「配偶者控除」とは全く異なる制度であるため、混同しないよう注意が必要です。前者は相続税の計算で適用される特例であり、後者は所得税の計算で適用される控除ですそのため、相談前には基礎的な知識を持っておくことが重要です。
また、配偶者が受け取る遺産が1億円を超えるかどうかによって、特例適用後の税率や税額が大きく変わるため、「どの財産を誰が相続するか」を慎重に決める必要があります。例えば、金融機関の預貯金だけでなく、不動産、法人株式、事業資産などが含まれる場合は分割が非常に複雑になります。資産価額の見積もりや、課税価格の算出に際しても専門的な知識が求められます。
さらに、遺産分割協議がまとまらないケースや、相続人に未成年者が含まれる場合、家庭裁判所の手続きが必要となるため、通常よりも時間と費用がかかります。万が一、遺産分割が相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)に間に合わない場合は、申告時に「未分割」である旨を記載し、後日「更正の請求」を行う必要があります。
相談時には、遺産の評価資料、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺言書の写しなどを事前に準備しておくと、専門家との打ち合わせがスムーズに進みます。これにより、調査や説明の手間が軽減され、より的確なアドバイスを受けることができます。
なお、2024年以降の税制改正により、税率や課税対象の条件が見直される可能性もあるため、最新情報の確認は欠かせません。全国各地にある税理士法人の中には、初回無料相談を実施している事務所もあるため、「気軽に問い合わせて、手順を把握する」ことが、結果的に大きな解決策へとつながるのです。
トラブルを避けるためにも、「いずれ分ければいい」ではなく、「今、どのように分けるべきか」を専門家と一緒に考えることが大切です。遺産相続は一度きり。正しい知識と準備で、将来の不安を減らし、家族全員にとって納得のいく相続を実現しましょう。
生前のうちに相続について準備しておくと安心

相続税の基礎控除は法定相続人の数によって決まり、法定相続人が誰になるかは、被相続人の家族構成によって決まります。相続放棄した人がいる場合でも基礎控除の金額は変わりませんが、養子がいる場合には実子の有無によってカウントできる人数が変わるため注意が必要です。
相続に関する相談は、全国の税理士事務所や行政サービスで受け付けており、地域に応じた対応が可能です。税理士法人の中には、初回無料相談やオンライン予約を導入しているところも多く、東京だけでなく、地方都市や中山間地域でも利用しやすくなっています。
また、各人の財産や家族構成によって、最適な相続対策は異なります。資産の割合が不動産に偏っている場合や、子供が複数いる場合には、「いくら渡すか」ではなく「どのように分けるか」が大切になります。
財産が2,000万円未満であっても、税務署への申告が必要となるケースや、葬式費用の扱いなど、実際の業務にはさまざまな注意点があるため、事前に「カテゴリ」ごとの対策を把握し、必要に応じて専門家への問合せを行いましょう。
相続税が「ゼロ」であっても、申告が不要というわけではありません。たとえば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用して「結果的に納税額ゼロ」となる場合は、申告しなければ特例が受けられません。実際には申請手続きが必要なケースがほとんどであり、放棄や未分割といった「形式の違い」が税務処理に影響を与えることもあります。
このように、「不要」と判断して申告を行わなかったことでペナルティを受ける事例もあるため、専門家との相談は欠かせません。
相続税の計算においては、対象になる財産の範囲が定められており、生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象財産になります。ただし、基礎控除とは別に非課税枠が設けられているため、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。
相続はいつ起こるか予測できないことだからこそ、両親が元気なうちに家族で話し合っておく必要があるといえるでしょう。
【ここをクリック】相続について漠然とした悩みをお持ちならソナミラのFP相談へ
▶【関連記事】相続税の計算はどう行う?税金がかかるとき、かからないときも解説
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

相続税の申告手続きに関してはこちらも参考になります。
知らないと損する控除制度まとめ|ベンナビ相続
▼参考資料
基礎控除の計算式
出典:国税庁 財産を相続したとき
法定相続人の範囲
出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
相続税がかかる財産
出典:国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
相続税がかからない財産
出典:国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号

 FP相談予約
FP相談予約