がん保険はいらない?必要性や不要な人の特徴、加入時のポイントを解説

がん保険が本当に必要なのか、あるいはいらないのか…その判断は簡単ではありません。罹患率や治療費の実態をふまえても、必要性を感じる人もいれば、そうでない人もいます。
この記事では、必要性の見極め方、理由や判断基準、がん保険の内容を紹介しながら、加入を検討すべき人の特徴などを解説します。
保険会社によって、各種の保障内容や特約の組み合わせが異なるため、内容をよく比較検討しましょう。
【ここをクリック】がん保険に疑問をもったならソナミラでFP相談してみよう
がん保険の必要性は「治療の選択肢」
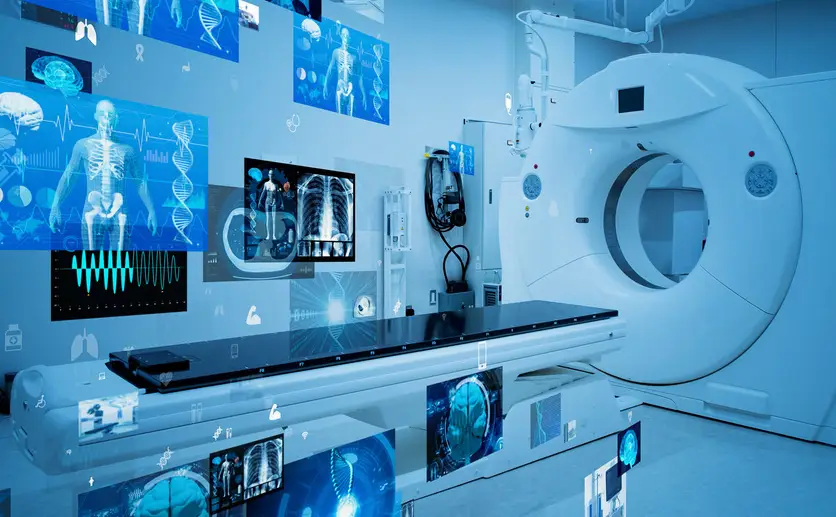
「全国がん登録」制度が2016年1月にスタートし、がんと診断された人のデータが国立がん研究センターで集計・分析・管理され、がん医療の体制づくりやがん対策に役立てられています。
そのデータをみると、 日本人の死因の第1位はがんであり、日本人の2人に1人が一生のうちにがんにかかるとされています。特に40代や50代を過ぎると、大腸がんや胃がんなどに罹患する可能性は高まっていきます。また、乳がんや子宮がんは比較的若い年齢でもかかります。このように生涯でかかる確率は決して低くありません。だからこそ、早い段階での備えが重要になります。
そして、がん保険の必要性は、罹患した後の治療方法に、より多くの選択肢を持つことにあります。がんにかかった際のリスクについて理解を深め、がん保険がどのような場面で活用されるのかを見ていきましょう。
高額になりがちな医療費を補完できる
がんで入院や手術をする場合、ほかの病気やケガと同様に公的医療保険が適用されるため、実際に医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は6歳以上70歳未満の場合、基本的には3割です。
また、「高額療養費制度」を利用することで、1か月(月初から月末まで)の自己負担限度額を超過した分の支給を受けられます。公的医療保険や高額療養費制度があれば、医療費の自己負担額を一定以下に抑えられることから、なぜがん保険が必要なのか疑問に思う人もいるでしょう。
しかし、がん治療は長期化することが少なくありません。実際、 再発や転移の可能性があるため、 長期間の治療が必要なケースも多いのです。
がんは、術後5年間、再発がなければ完治したものとみなすケースが一般的です。したがって、治療が長期化すれば、その分金銭的な負担が増えてしまいます。
また、入院時に少人数部屋や個室を希望すれば、「差額ベッド代」を支払わなければなりません。差額ベッド代は公的医療保険制度の対象外となるため、全額自己負担です。
厚生労働省の「中央社会保険医療協議会 総会(第548回) 主な選定療養に係る報告状況」によると、差額ベッド代の平均額は1日あたり6,620円です。がん保険に加入すると、これらの費用を幅広くカバーできるため、経済的な不安が減り、安心して治療に専念できるようになるでしょう。
療養中の生活費を補填できる
がん罹患時は、治療をするために仕事を休まざるを得ないケースもあります。がん治療が一段落しても、体力が低下してしまい、がんと診断確定される前と同じような仕事のパフォーマンスが発揮できず、離職を余儀なくされるケースもゼロではありません。治療費の増加と収入の減少により、生活が苦しくなる場合もあるでしょう。
また、治療が長期化した場合、通院や生活面の介護的な支援が必要になるケースもあります。がん治療中の 就業が困難になれば、生活費負担やローンの返済が課題となります。就業不能状態が長引くと、収入減少により家計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
がん保険では、がん診断給付金(一時金)で診断後の生活に備えることができるほか、療養中に定期的に給付金を受け取ることも可能です。これらの給付金は使い道が自由で、治療費はもちろん、毎月かかる生活費や家賃、ローンなどの固定費の支払いなどにも充てられます。がん保険に加入していれば、療養中の生活費に感じる不安を減らし、治療に専念できるでしょう。
治療の選択肢を広げることができる
近年では医療技術の進歩により、自由診療や先進医療など選択肢が広がっています。
がんの治療法、罹患した部位、がんの種類や進行度合い、患者の希望などによって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
● 標準治療
科学的根拠に基づいて効果が認められた治療で、公的医療保険が適用されます。手術、放射線治療、抗がん剤の治療などが含まれます。たとえば乳がんの場合、手術後に放射線治療やホルモン療法が必要となることがありますが、これらは標準治療の範囲内です。
そして、治療の方針によっては、次に説明する先進医療や自由診療を選択する可能性もあります。
● 先進医療
厚生労働大臣が承認した高度な医療技術を用いた治療で、保険診療との併用が認められていますが、技術料に関しては公的医療保険の対象外*1です。
代表的な治療方法として、重粒子線治療や陽子線治療などがあります。
● 自由診療
有効性が公的に確認されていない治療方法であるため、公的医療保険が適用されません。海外で通常行われていても日本国内で承認されていない治療や、国内未承認の薬剤や医療機器を使った治療などが含まれます。
*1「先進医療に係る費用」は全額自己負担ですが、標準治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用には健康保険が適用されます。先進医療や自由診療は、数十万円~数百万円単位の高額な自己負担が一時的に必要になるケースも少なくありません。がん保険に加入していれば、これらの治療費をある程度カバーでき、費用面を気にし過ぎることなく治療方法の選択肢が広がります。
がん保険が必要な人の特徴

がん治療は本人だけでなく、家族や身近な人の生活にも大きな影響を与えます。そのため、万が一に備えてがん保険に加入しておくと安心です。以下にあげる特徴が当てはまり、個人で対策を立てたい人は、がん保険への加入を検討してみましょう。
がんの医療費の支払いに不安がある人
がんになると、高額な治療費が生活費を圧迫します。とくに、貯蓄が少ない人や、いざというときの金銭的な備えが少ないは、がん保険の必要性が高いと言えます。
また、自営業者や個人事業主が一般的に加入する国民健康保険では、企業に勤める会社員のように、傷病手当金を受けることができません。傷病手当金とは、会社員や公務員などの健康保険に加入している方が、病気などの療養により会社を休み、十分な収入が得られない場合に、給料の約3分の2の給付を受けられる制度です。
国民健康保険では、傷病手当金の制度がありません(一時的に制度が設けられることもあります)。そのため、がんに罹患して働けなくなると、収入が大きく減少する可能性が高まります。
がんにかかった場合の医療費や生活費の支払いが心配な人は、がん保険に加入するなど、万が一への備えが大切です。
生活習慣が乱れている人
がんは、生活習慣と密接な関係がある病気です。国立がん研究センターによると、飲酒によって体内に取り込まれるエタノールは、がんの原因になると考えられています。
また、肥満は、インスリンやエストロゲンなどのホルモンが過剰に分泌され、がん細胞の増殖を促進すると言われています。
生活習慣の中でも、とくにがんのリスクを高めるとされているのが喫煙習慣です。特に肺がんの発症リスクを高めるとされています。国立がん研究センターによれば、喫煙は男女ともにがんリスクを高めるとされています。タバコは、ニコチンやタールなどの有害物質を含み、肺や呼吸器、消化器などにがんを引き起こす可能性があります。
がんになった人のうち、男性の約24%、女性の約4%はたばこが原因とされています。
がんは早期発見・早期治療が重要ですので、定期的な健康診断やがん検診を受けることを忘れないようにしましょう。
がん保険が不要な人の特徴

がん保険は必ずしもすべての人に適した保険とは言い切れません。特に、以下に当てはまる人であれば、がん保険による備えは必要ないと考えられます。
医療費の支払いに不安がない方
余裕を持って治療費を支払えるだけの十分な貯蓄がある、あるいは株式や不動産などの資産収入を得られる場合など、がんになったとしても大きく収入が減るリスクの少ない方は、がん保険に加入する必要性は低いと言えます。
がん保険で後悔しないように次の記事もあわせて参考にしてください。
▶【関連記事】がん保険で後悔したことは?加入の必要性や入っていないリスク
▶【関連記事】「がん保険に入っておけばよかった」と後悔する前に知っておきたいこと
がん特約を十分に付加している方
すでに加入している医療保険にがん特約を付けている人は、改めてがん保険に加入する必要はないでしょう。なぜなら、がん保険と同等の保障内容を備えているがん特約も少なくないからです。
複数の保険会社で同様の保障に加入している場合、支払い事由に該当すれば、それぞれの保険会社から給付金を受け取れることになります。そのため、保障を手厚くすることが無駄になるわけではありません。一方で、加入している保険が増えればその分保険料の負担も増えるため、家計とのバランスを考慮したほうが良いでしょう。
【ここをクリック】がん保険が必要かわからない人はソナミラのFP相談で確認!
がん保険へ加入するときのポイント

がん保険へ加入するときは、どのようなことに注意すべきでしょうか?ここでは、がん保険へ加入するときのポイントについて4つの観点から説明します。
上皮内新生物が保障されるか
がん保険に加入する際は「上皮内新生物」が保障対象に含まれているかを確認しましょう。上皮内新生物は、体の皮膚の表面や臓器の粘膜などを覆っている「上皮」にがん細胞がとどまっている状態のことです。初期のがんと言われており、一般的ながん(悪性新生物)と区別されています。
がん保険によっては、診断給付金の額が悪性新生物の半分程度あるいは10%程度と、上皮内新生物に対する保障が制限されているケースも少なくありません。また、過去に販売された商品の中には、上皮内新生物の保障がない場合もあります。すでにがん保険に加入している人でも、契約してから長期間経過している場合は、保障内容を見直したほうが良いでしょう。
先進医療に対応しているか
がん保険を選ぶ時のポイントの一つとして、先進医療に対応しているかどうかを確認することが重要です。先進医療特約が付いていれば、がんになった場合に治療の選択肢が広がり、負担を軽減することができます。
先進医療にかかる技術料は全額自己負担*2となるため、費用負担が高額になるケースは珍しくありません。例えば、陽子線治療の場合、1件当たり平均で270万円もの費用がかかります。また、先進医療はどの病院でも受けられるわけではなく、厚生労働省が定める施設基準を満たした医療機関でのみ実施されています。
*2「先進医療に係る費用」は全額自己負担ですが、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用には健康保険が適用されます。先進医療特約では、先進医療の技術料に対して2,000万円程度まで保障するケースが一般的です。また、先進医療を受ける際にかかる交通費や宿泊費などをカバーできる一時金が支払われる商品もあります。
がんの4大治療の保障が手厚いか
国立がん研究センターの『がん情報サービス』は、がんの種類や治療法について詳しく解説されており、非常に役立つサービスです。
これらの情報によると、がんの治療法は主に「手術療法」「放射線療法」「化学療法」「免疫療法」の4つに分かれます。がんの種類や進行度合いによって用いる治療法は異なり、場合によっては2つ以上の治療法を組み合わせることもあります。4つの治療方法に対してそれぞれ手厚い保障がついていれば、治療方法が変わった場合も給付金を受け取りやすくなるため、がんにかかる医療費を補完できます。
1回治療を受けるたびに所定の給付金を受け取るタイプと、治療を受けた月ごとに給付金を受け取るタイプが主流です。入院、通院に関係なく支払われるか、保障金額や支払回数の上限はどのくらいか、自由診療や先進医療も保障対象になるかなども確認しておきましょう。
貯蓄が少ない場合は一時金があるか確認する
がんと診断された場合は、治療のため働くのが難しくなり収入が減る可能性が高まる一方で、治療費の負担は増えていきます。そのため、貯蓄が少ない状態でがんにかかってしまうと、経済的に困難な状況に陥る可能性があります。さらに、大きな精神的なストレスを感じるかもしれません。
がん保険に加入する際は、がんと診断された段階でまとまった給付金を受け取ることができる「一時金」の保障が含まれているかを確認しておきましょう。一時金は使い道が決められていないため、入院費や手術費、不足する生活費の充当などに幅広く使えます。
がん保険を選ぶにあたって後悔しないよう次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】後悔しないがん保険の選び方は?基礎知識と年代別のポイント
がん保険に関するよくある質問
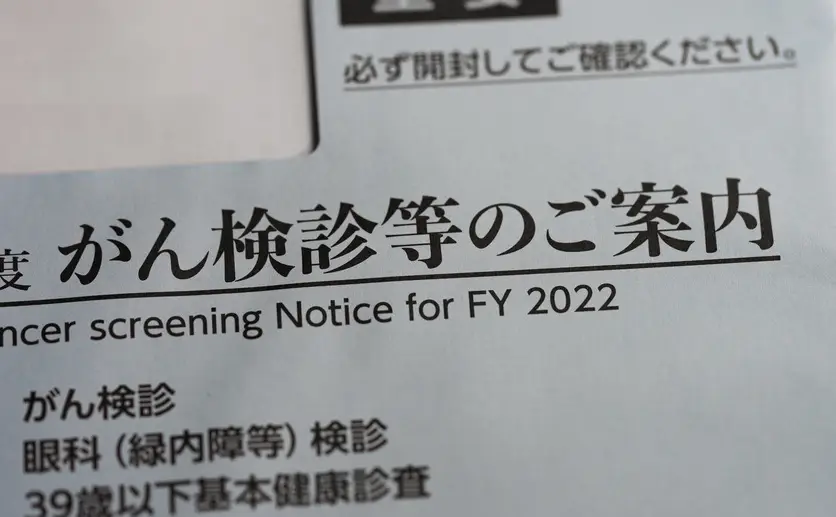
がん保険に関連する、質問とその回答をまとめました。がんに備える手段として、がん保険の必要性を真剣に検討している方や、がん保険について疑問や不安がある方はぜひご覧ください。
がん保険はいつまでに入っておくべきですか?
がん保険に関しては、いつまでに入っておくべきかという明確な基準はありません。
若い世代でもがんになる可能性はゼロではありませんし、健康状態が悪化してからでは加入できなくなる可能性もあります。年齢を重ねるほど病気になるリスクが高まりますので、加入時の年齢が若いほど、保険料を抑えて加入できるケースが一般的です。
がん保険は何のために必要ですか?
がん保険は、がんになったときの入院費や手術費などの費用を補うために必要です。がん療養中に収入が減った場合の生活費も含めてカバーすることができます。さらに、自由診療や先進医療など、費用が高額になりがちな治療も受けやすくなり、治療の選択肢も広がります。
自由診療について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
▶【関連記事】がんの自由診療とは何?がん保険を検討する前に知っておきたいこと
医療保険とがん保険どちらに入ったほうがいいですか?
一般的には、医療保険に優先的に加入したほうが良いとされています。がん保険の保障の対象は原則として「がんのみ」である一方で、医療保険はがんでの入院や手術に対する保障が付けられるためです。ただし、がん保険は医療保険よりもがんに対して手厚く備えられる特徴があります。
可能であれば、両方加入しておくのがおすすめです。保険料の負担は増えますが、幅広い病気やケガに備えつつ、がんに対する保障も充実させられます。
また、どちらの保険も契約時の条件によっても、保障の範囲や給付金額が異なるため、内容をよく確認しましょう。いずれにしても、がん保険と医療保険の違いを理解して、適切に選ぶことが重要です。
がんになった人でも入れる保険はありますか?
過去にがんと診断された人でも、加入できる商品はあります。ただし注意点は、がんの状態や治療の経過などによっては加入できない場合もあることです。代表的なものとしては、一般的な生命保険よりも健康告知項目が少ない傾向にある「引受基準緩和型」の商品や、健康状態に関する健康告知が不要な「無選択型」の商品などがあげられます。
これらの商品は、一般的な生命保険と比べると、保険料が割増されていたり、一定期間の支払削減期間が設けられていたりなど、いくつかの制約がある場合も少なくないので、保障内容をよく確認してから加入しましょう。
がん保険に加入できないのでは?と心配になる人は次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】がん保険に入れない人はどうしたら良い?加入できないケースと対処法
がんの治療費は平均していくらかかりますか?
がんの治療費は他の疾病と比べて高くなる傾向があります。
実際に厚生労働省の「令和3年度医療給付実態調査」によると、がんで入院した場合にかかる「1日当たり診療費(診療費÷診療実日数)」の平均は78,525円、通院した場合は43,155円です(どちらも協会けんぽ加入者のデータ)。
ほかの病気も含めると入院した場合が平均60,246円、通院の場合は平均9,330円であることから、がんにかかるとほかの病気と比べても治療費が高くなる傾向にあります。
がん保険の必要性はその人次第

がんは日本人が死亡する原因として一番高い疾患です。 がんになるリスクや経済的影響を考慮すると、がん保険で備えることは重要です。十分な収入や貯蓄がある場合は、がん保険の必要性は低いですが、治療費に不安がある場合は加入をおすすめします。
がん保険に加入すべきか分からず、自分だけで判断するのが不安な人は、保険の専門家へ相談することも検討しましょう。がん保険はさまざまな商品があるため、ご自身の状況に合った内容を選ぶことが大切です。
人生のライフステージごとに、必要な保障内容は変わります。「今はがん保険は不要」と判断した人も、今後の状況の変化によっては必要になることを理解しておくとよいでしょう。
ソナミラでは店舗やオンラインで保険の無料相談を行っています。家計の状況や将来のライフプランを考慮したうえで、経験豊富なコンシェルジュから、どんながん保険やプランが自分に合っているか、アドバイスを受けられます。興味ある方はお気軽に相談してみてください。
【ここをクリック】がん保険を一覧で見たい人、相談したい人はソナミラへ
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考
2人に1人以上ががん
出典:国立がん研究センター 最新がん統計
がん保険に加入している人は全体の約4割
出典:公益財団法人 生命保険文化センター 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査
高額療養費制度について
出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
差額ベッド代の平均額
出典:厚生労働省 主な選定療養に係る報告状況
標準治療について
出典:国立がん研究センター 標準治療と診療ガイドライン
先進医療について
出典:厚生労働省 先進医療の概要について
自由診療について
出典:再生医療ポータル 自由診療(じゆうしんりょう)
傷病手当金について
出典:全国健康保険協会 傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する 傷病手当金の支給について
出典:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について(その2)
がんの発生要因
出典:国立がん研究センター がんの発生要因
がんの発生や治療へのたばこの影響
出典:国立がん研究センター がんの発生や治療へのたばこの影響
先進医療にかかる技術料
出典:厚生労働省 令和5年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について
1日当たり診療費(診療費÷診療実日数)」の平均
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)医療給付実態調査 報告書 令和3年度

 FP相談予約
FP相談予約











