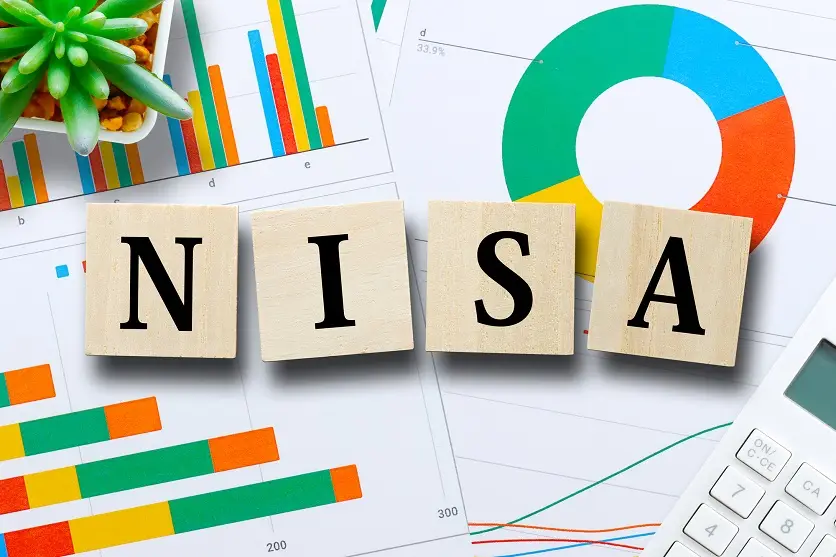NISAを始めるタイミングを解説!つみたて投資枠のメリットと始め方は?

将来に向けた資産形成を行ううえで、NISAの活用はとても重要です。特に2024年からの制度改正により、より多くの人が非課税の運用益を享受できる環境が整いました。
「NISAで積み立てを始めたいけれど、損はしたくない」「始めるのにベストなタイミングはあるのか」といったことが気になっている投資初心者も多いでしょう。実際のところ、NISAは「思い立ったときに始める」のが最も効率的と考えられます。早く始めれば、より多くの利益を目指せるかもしれません。
この記事では、NISAを始めるべきタイミングを詳細に解説します。具体的な始め方や手続きの流れも紹介しますので、NISAを活用して資産運用をスタートさせたいと考えている人は参考にしてみましょう。
【ここをクリック】NISAの始め時は?悩んだらソナミラでFP相談してみよう
NISAで積立投資を始める適切なタイミング

NISAの新制度では、これまで以上に長期的な視点での資産形成が重視されています。2024年より非課税期間が無期限になったことで、 短期的な市場の変動に左右されず、長期的な資産成長を見据えた投資が可能になりました。
NISAの認知度が高まっている大きな理由は、こうした利便性の向上だけではありません。日本での将来的な年金不安や物価上昇が問題となっているからです。その対策の一つとして、多くの専門家もNISAの活用を強く後押ししています。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの非課税枠があり、両方もしくはどちらか一方のみを利用して運用します。ここでは、つみたて投資枠の特徴を確認しながら、積立投資を始めるのに適したタイミングを確認していきましょう。
つみたて投資枠は長期分散投資
NISAは、投資で得た利益に対して税金がかからなくなる制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品を購入し、売却益や配当金、分配金が発生した場合、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が課されます。しかし、NISA口座で取引をすれば、これらの税金は一切かかりません。
さらに、つみたて投資枠とは、少額から始められる長期・積立・分散投資を支援する、NISAの非課税投資枠のひとつです。つみたて投資枠を使って、投資信託やETFなどを積立購入した場合に、売却益や分配金を非課税で受け取れます。
長期的な視点に立った資産運用に適しており、分散して投資することによってリスクの軽減が期待できます。株価や為替の変動に一喜一憂せず、たとえ暴落が起きても途中でやめずに継続することが何よりも重要です。
また、少しずつ積み立てることになるため、無理のない範囲で投資ができます。住宅ローンの返済なども考慮に入れながら、家計の収支状況に応じて着実に長期投資を続ければ、効率的に資産をふやせるでしょう。
つみたて投資枠では年間120万円、月当たりに換算すると10万円まで非課税で投資でき、一生涯を通じた非課税保有限度額は1,800万円です。これは成長投資枠と合わせた限度額であり、つみたて投資枠のみを利用して1,800万円の上限枠を使い切ることもできます。
非課税保有期間は無期限となっており、数十年の長期運用で多くの利益が出たとしても、税金は一切かかりません。
なお、積立投資する際の最低金額は金融機関によって異なりますが、投資信託であれば毎月100円から始められるケースもあります。
積み立てを始める適切なタイミング
「いつ始めればいいの?」という声は多くありますが、できるだけ早く始めることが運用効率の面でも有利です。例えば、2022年から始めた人と2025年に始めた人では、運用益に大きな差が出る可能性もあります。迷っているのであれば、思い立ったタイミングで始めてみるのも、有効な選択肢のひとつです。
高値が続いている時に商品を購入すると、あとで価格が下落して損失を出してしまうのではないか、と不安になる人もいるかもしれません。しかし、毎月一定額を購入する積立投資には、価格変動リスクを抑える効果があります。
簡単な例で、シミュレーションします。
たとえば、毎月1万円で投資信託(1口=1円)の積み立てを開始し、基準価額(1万口あたりの価格)が1か月目は1万円、2か月目は5,000円、3か月目は2,000円と変化した場合、3か月間の投資額3万円に対して購入口数の合計は、1か月目・1万口+2か月目・2万口+3か月目・5万口=8万口です。ここで、4か月目に基準価額が5,000円になったタイミングで売却したとすると、売却額は5,000円×8(万口)=4万円です。つまり、売却額4万円―投資額3万円=1万円の利益を得られます。
一方、同じ金額を1か月目にすべて投資した場合、投資額3万円に対して基準価額は1万円ですから、購入口数は合計3万口となります。先ほどと同じように4か月目に基準価額が5,000円になったタイミングで売却したとすると、売却額は1万5,000円となり、1万5,000円の損失が出ます。
つまり、毎月一定額を積立投資することによって、値下がりしている時には多く購入し、値上がりしている時には少なく購入することになるため、平均購入単価が平準化されていき、価格が元の水準にまで戻り切らなくても利益を得られる可能性が出てくるということです。このように、定額で購入する方法は「ドル・コスト平均法」と呼ばれます。
購入した金融商品の価格が下落し続けた場合は損失が出る場合があり、積立投資はあらゆる相場においても有効とは限りません。ただし、値動きを過度に気にする必要がないという点で、積み立てを始めやすくなるでしょう。
また、なるべく早く積み立てを始めた方が投資期間を長く確保でき、複利効果を最大限活用できるというメリットもあります。複利効果とは、運用で得た利益を再び投資に回すことで、お金がふえていく効果のことです。
投資した元本のみに対して利子がつくことを「単利」と呼ぶのに対して、複利では元本と利子を合計したものに利子がつきます。つまり、利子が利子を生む状態になるのです。これによって時間が経過するほど、お金が雪だるま式にふえていく仕組みになっています。
つみたて投資枠で購入する投資信託の多くは、分配金が自動的に再投資される仕組みのため、複利効果を得やすい点も魅力です。
つみたて投資枠を上限まで使い切るなら、1月から始めて、毎月10万円ずつ積み立てると良いでしょう。ただし1月以外の時期に始めたとしても、ボーナス月や指定した月の積立額をふやせる「ボーナス設定」「増額設定」を活用することで、年間投資枠を使い切ることはできます。
ただ、積立投資への理解が不十分で高い利回りばかりを狙いすぎて、短期的な下落局面で急いで売却してしまうなど、運用に問題が生じている人も中にはいます。基本には忠実に、長期間コツコツ投資を行うことが最も効率的であると認識して始めましょう。
2024年のNISAの制度改正について知りたい方はこちらも参考にしてください。
▶【関連記事】新NISAとは?2024年制度改正において知っておきたい変更点とメリット
また、長期投資する際の時間分散効果についてはこちらを参考にしてください。
▶【関連記事】長期投資をするときに覚えておきたい「ドルコスト平均法」とは?
iDeCoとの違いを理解しよう
NISAと同じく将来の資産形成に活用できる制度として、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」もよく比較の対象になります。どちらも 《目的》は「長期的な資産形成」ですが、その仕組みや使い方には大きな違いがあります。
まず、iDeCoは原則60歳まで資金を引き出すことができません。一方、NISAはいつでも換金が可能で、資金の流動性が高いという特長があります。家計に余裕がない局面でも、NISAであれば柔軟に対応できる点が魅力です。
また、税制上の優遇にも違いがあります。iDeCoでは毎年の掛金が所得控除の対象となり、税金の軽減効果が高い反面、運用益や給付金にも税制優遇措置が適用されます。一方、NISAは運用益が非課税となる点でシンプルでわかりやすい制度設計といえるでしょう。
さらに、iDeCoは私的年金制度のひとつであり、加入者が国民年金、厚生年金などの制度に応じて上限金額が異なります。自営業者や専業主婦(夫)、会社員、公務員など、勤務形態によって条件が変わる点は注意が必要です。運用に必要な手数料もiDeCoでは口座管理費などがかかるため、事前に確認しておくと安心です。
NISAとiDeCoは、どちらが優れているというよりも、 目的やライフステージ、使い道に応じて併用するのがおすすめです。専門家やFPに相談しながら、自身に合った制度を選びましょう。
保険との役割分担も考える
NISAは資産運用を通じてお金をふやすことを目的とした制度ですが、人生には投資だけでは対応しきれないリスクもあります。たとえば、病気や事故による入院、万一の際の家族の生活費確保などには、やはり保険の備えが欠かせません。
NISAは原則として「自分の意思で運用を行い、将来の資産形成を目指す」ための制度です。一方、保険は万が一の事態に備える保障機能があり、目的や性質が根本的に異なります。つまり、この2つは対立するものではなく、むしろ役割分担を意識した併用が理想です。
たとえば、住宅ローンを抱えている場合、死亡保険や収入保障保険を使いながら万一に備える一方で、将来の教育資金や老後資金に向けてNISAで資産をふやしていくという戦略が考えられます。費用をかけすぎず、バランスの取れた設計にするには、毎月の家計の管理が重要となるでしょう。
また、NISAは途中で解約することも可能ですが、医療保険などは契約途中での解約によって損失が出る場合もあります。それぞれの制度の特徴や条件をよく比較しながら、どこまでをNISAに任せ、どの範囲を保険でカバーするのかを判断することが大切です。
保険と投資、どちらも生活に欠かせない金融商品です。自分や家族のライフプランに応じて、余裕を持った設計を目指しましょう。
NISA運用のコツと今後の見通しを押さえよう

NISA制度は2024年に大きく改正されましたが、それ以降の経済状況や市場の動きによって、投資成果は大きく左右される可能性があります。ここでは、投資環境を整理し、NISA運用のコツと今後の見通しを解説します。
2025年以降の投資環境を見据えよう
2025年以降も金利の上昇や物価の変動、為替の影響など、投資する上で注目すべき要素が多くなると予想されています。
特に注視すべきなのが、米国や日本の中央銀行による金融政策です。金利が高くなれば債券価格が下がったり、企業の業績が悪化して株式市場に影響が出ることも考えられます。このような状況では、投資初心者ほど「いつ始めるべきか」「今はやめておくべきか」と悩みがちです。
しかし、NISAのような長期の非課税制度は、市場の短期的な動向に一喜一憂するよりも、分散投資と時間を味方につける戦略が有効です。ドル・コスト平均法のように毎月一定額を積み立てる方法であれば、高値掴みのリスクを抑えつつ平均取得単価を平準化できます。
また、2025年以降もNISAの人気はさらに高まると考えられています。金融機関等のセミナーによる情報提供も増えており、検索すれば関連するサービスや情報を容易に得られるようになりました。余裕範囲内で投資を継続し、家計を圧迫しないことが大切です。
NISAとポートフォリオ管理の基礎
NISAを活用して安定的な資産形成を目指すには、金融商品の選び方だけでなく、ポートフォリオ全体の管理が重要です。ポートフォリオとは、保有する金融商品の組み合わせことであり、「何に、どのくらい投資するか」を設計する考え方を指します。
例えば、すべての資金を国内株式に集中させてしまうと、国内要因の市場動向に大きく左右されるリスクがあります。これを防ぐために、国内外の株式や債券、REIT(不動産投資信託)など、さまざまな金融商品を組み合わせることで、分散効果が生まれます。
また、NISAでは非課税枠の上限を意識しながら、どのタイミングでどの商品を取得するかもポイントになります。例えば、株式市場の下落局面で株式型のファンドを、金利が上昇している局面では債券ファンドを積み増すことで、ポートフォリオのバランスを調整する戦略も考えられます。
「リバランス」も重要な運用テクニックです。リバランスとは、当初設定した資産配分の割合に定期的に戻す作業のことです。例えば、最初に株式60%・債券40%で投資を始めたとしても、株式が値上がりすると、いつの間にか株式70%・債券30%といった配分に変化してしまいます。この状態を放置すると、意図せず株式のリスクが高まった状態で運用を続けることになります。
定期的に資産配分を見直し、当初設定した割合に戻すことで、高くなった資産を売って安くなった資産を買うという「高く売って安く買う」投資の基本原則を実践できます。
ポートフォリオを構築する際は、年齢や収入、投資目的に応じたリスク許容度を考慮することが重要です。若年層であれば株式比率を高めに、退職が近い方は債券比率を高めにするなど、ライフステージに合わせた資産配分を検討しましょう。
初心者の方は、「リスクが高くてもリターンが大きそうな商品を選べばよい」と考えがちですが、それは失敗のもとになりかねません。目的や家計の状況を考慮し、無理のない範囲で運用を行いましょう。
NISAの失敗事例から学ぶ
NISAは非課税という大きなメリットがありますが、使い方を誤ると期待した効果が得られないこともあります。よくある失敗事例から注意すべきポイントを整理しておきましょう。
まず多いのが、「リスクが高くても短期間で大きな利益を得たい」と考え、情報だけを頼りに流行の銘柄に集中投資してしまうケースです。こうした場合、価格が下落した際に精神的に耐えきれず、損をした状態で売却してしまうことが少なくありません。目的が明確でないまま始めると、このような事態を招きがちです。
また、NISA口座を開設したものの、「積立設定を忘れていた」「投資商品を選ばずに放置していた」といった、せっかくの制度を十分に活用できていないという声もあります。制度を理解し、前提となる仕組みをきちんと押さえておくことが重要です。
さらに、「費用がかからないから安心」と考えていても、投資信託には手数料が発生するものもあり、実質的な運用コストに気づかないまま保有を続けてしまう人もいます。手数料の一覧を比較し、金融機関の販売担当者の説明などを参考にしながら、商品ごとの条件をきちんと確認してから選ぶようにしましょう。
NISA(つみたて投資枠)の始め方
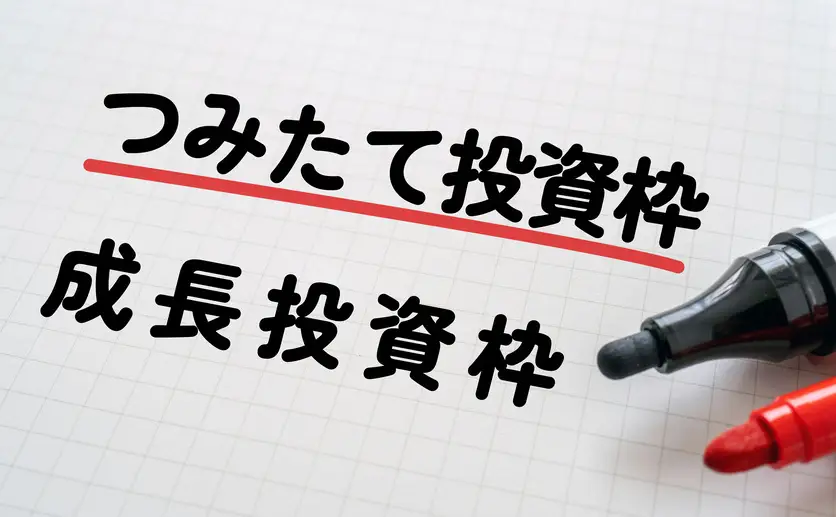
ここではNISA(つみたて投資枠)を始める方法を解説します。全体像を理解しておくと、実際に始める際もつまずきにくくなるでしょう。
STEP1. 金融機関を選ぶ
まずはどの金融機関でNISAを始めるかを決めましょう。NISA口座は、銀行や証券会社などで開設できますが、すべての金融機関を通じて1人1口座しか作れません。金融機関によって購入できる金融商品や最低積立金額が異なるので、慎重に選びましょう。
STEP2. 口座を開設する
金融機関を選んだら、窓口またはオンラインで口座を開設します。
オンラインでは、サイトやアプリを通じて、申込みが可能です。金融機関ごとに条件や手続きが異なるため、表や比較資料でそれぞれを見て選ぶと良いでしょう。
申し込みの際は運転免許証などの「本人確認書類」、マイナンバーカードや通知カードなどの「マイナンバー確認書類」の提出を求められるケースが一般的です。
なお、NISA口座の開設にあたっては金融機関と税務署によって、審査が行われます。金融機関ごとに定められた基準を満たしていない場合や、ほかの金融機関でNISA口座を開設済みの場合は、審査を通過できない場合もあるため、注意しましょう。
STEP3. 投資商品を決める
口座を開設したら、投資する商品を選びましょう。目論見書などを通じて、投資対象やリスク、運用実績などをチェックします。
STEP4. 積立設定をする
投資する商品を選んだら、毎回の積立額や積立頻度を選択しましょう。金融機関によって、最低積立額には開きがありますが、投資信託であれば100〜1,000円程度から積み立てを開始できるケースが一般的です。
また、毎月1回の積み立てだけではなく、「毎週」や「毎日」の積み立てに対応している場合もあります。一部のネット証券では、クレジットカードでの決済に対応している場合もあるので、確認しておきましょう。
NISAのつみたて投資枠を利用する際の注意点

NISAでつみたて投資枠を利用する際は、成長投資枠との違いや、NISAの根本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
投資できる商品が定められている
つみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁の基準を満たした投資信託やETFのみです。具体的には、長期の積み立てや分散投資に適した銘柄が厳選されており、頻繁に分配金が支払われる投資信託などは除外されています。
言い換えるならば、つみたて投資枠は対象商品の選択が強制されています。一方で成長投資枠では、個別株やETFを含め幅広い商品から選択が可能です。このようにNISAのつみたて投資枠と成長投資枠には「壁」となるような制度的違いもあるのです。この点を把握し、参考情報を集めた上で運用を始めることが重要です。
個別株式やつみたて投資枠対象外の投資信託など、幅広い銘柄を購入したい場合は、成長投資枠を活用しましょう。
元本割れのリスクがある
つみたて投資枠の投資対象は、金融庁が厳選した投資信託に限定されているため、安心して投資できるように思えるかもしれません。しかし、投資信託には銀行預金のような元本保証はなく、価格変動リスクがあります。そのため、基準価額が大きく下落し、売却時点で投資した金額よりも少ない金額しか戻ってこない「元本割れ」の状態に陥る可能性もあります。
投資の原則としては、長期間投資を続けることによって収益が安定し、元本割れするリスクを軽減できるというのを理解しておきましょう。
損益通算ができない
NISAでは、損失をほかの口座の利益と相殺して、課税額を減らす「損益通算」ができません。NISA口座での取引は、利益に対して課税されない反面、税法上損失がないものと見なされるためです。
また、控除しきれなかった損失を最大3年間繰り越しできる(利益と相殺できる)「繰越控除」も認められていません。
NISA口座で損失が出ていても、NISA口座以外の課税口座で利益が出ていれば、通常通り課税される点には注意が必要です。
NISAは早く始めるほどメリットが大きくなる

2024年から始まったNISAのつみたて投資枠では、年間120万円、一生涯で1,800万円まで非課税で投資できます。
積立投資には平均購入単価を平準化する効果があることから、始めるタイミングを気にしすぎる必要はありません。また、早く始めるほど、長期間運用できるため、複利効果によって期待できる利益も大きくなります。投資で得た利益が非課税になるというNISAのメリットを最大限に活かせるよう、まずはスタートしてみましょう。
NISAのつみたて投資枠を活用し、資産形成のベースを築くために、 自分に合った投資スタイルを考えることが大切です。
とはいえ、実際にうまく運用できるか不安な人もいるかもしれません。そんなときはお金のプロであるソナミラのコンシェルジュに相談してみましょう。ソナミラではIFAであるコンシェルジュに、NISAの活用方法を無料で相談できます。また、店舗だけではなくオンラインで手軽に相談することも可能です。NISAを始めるにあたって不安がある人は一度相談してみてはいかがでしょうか。
【ここをクリック】NISAを始めたい人はソナミラでFP相談してみよう
NISAに興味を持った方は次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】NISAは本当にデメリットしかないのか?FPが解説するNISAの真実とは
▶【関連記事】新NISAで投資信託orETF?FPが教えるお得な選び方とは
▶【関連記事】新NISAを始めるときに検討したい!クレカ積立で投資効果を高める
↓LINE友だち登録はこちら↓
教育費シミュレーションや保険・資産運用に関する情報をLINEで発信中!

▼参考資料
つみたて投資枠とつみたてNISA(旧制度)の比較
出典:金融庁「新しいNISA」
ドル・コスト平均法
出典:日本証券業協会 投資の時間「定額購入法(ドル・コスト平均法)(ていがくこうにゅうほう(どる・こすとへいきんほう))」
NISAで投資できる商品
出典:金融庁「つみたて投資枠対象商品の分類」
NISAのリスク
出典:金融庁「NISAガイドブック」
「NISA」って何?わかりやすく解説
出典:政府広報オンライン「令和6年(2024年)1月、「NISA」が新しくなりました!」
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号

 FP相談予約
FP相談予約